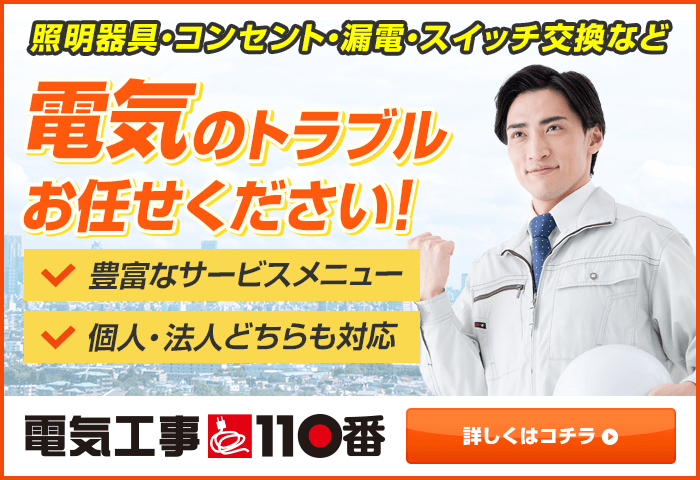新築住宅の電気工事とは?後悔しないために知っておくべきポイント
設計段階から関与する「電気工事の本質」
新築住宅を建てる際に、多くの人が注目するのは「間取り」や「キッチン・バス」などの設備ですが、実は暮らしやすさに直結するのは“電気工事”の質と設計です。
電気工事とは、住宅において電力を使える状態にするための一連の作業であり、具体的には以下のような工程が含まれます。
・ 分電盤の設置や回路設計
・ コンセント、スイッチ、照明の配線
・ インターネットやテレビ配線
・ インターホンや防犯設備の接続
・ 屋外電源やEV用コンセントの準備
これらは、家の構造と同時進行で設計され、完成後に修正することが非常に難しいのが特徴です。つまり、電気工事の良し悪しは「後からではやり直しがきかない」一発勝負とも言えるのです。
住み始めてから「後悔」しやすい3大要素とは?
1. コンセントの数が足りない・場所が悪い
「家具を置いたらコンセントが隠れてしまった」「掃除機のコードが届かない」などのトラブルは、新築住宅でも頻発します。この原因は、実際の生活動線を想像しきれずにコンセント位置を決めてしまったことにあります。
対策としては、各部屋に対して2〜3倍の使用想定でコンセントを配置し、家具配置とのバッティングも事前に確認しておくことが重要です。
2. スイッチの位置が遠い・操作が不便
「玄関から入ってすぐ照明がつけられない」「階段の上下で照明が操作できない」などの不便は、毎日の生活で小さなストレスを積み重ねる要因となります。
スイッチは、「どこに立っているときに使うのか」を明確にイメージし、移動中に“ついでに操作できる”位置に配置するのが理想です。さらに、寝室の枕元スイッチや、玄関の一括消灯スイッチなどもあると利便性が大きく向上します。
3. インターネット・テレビ配線の不備
近年は、スマートテレビ・Wi-Fi中継機・IoT家電など、通信環境に依存する機器が急増しています。ところが、設計時にLANケーブルの配線やテレビ端子の位置を疎かにしてしまうと、あとから壁に穴を開けて配線を引き直す羽目になります。
将来の機器増設を想定して、各部屋にLAN配線と空配管を設けておくのが賢明です。
電気工事のポイントは「事前の想像力」にあり
新築住宅の電気工事で後悔しないためには、次の3つの視点が極めて重要です。
1. 生活動線に合わせた配置設計
ただ「部屋に必要な数」ではなく、“どの場所で・どのタイミングで”使用するかを想定することが大切です。
例えばリビングでは、テレビ・加湿器・スマホ充電・ロボット掃除機など、1箇所で複数の電源が必要になる可能性が高いため、最低でも5〜6口のコンセントがあると安心です。
2. 将来の機器増設・使い方の変化に対応
子どもが大きくなれば部屋の使い方も変わりますし、EV車の導入や太陽光発電の設置など、家の外にも電気工事が必要になる場面が出てきます。
こうした将来の変化に備えるには、空配管・予備配線・分電盤の余裕回路を設けておくと柔軟に対応できます。
3. プロとの打ち合わせを“納得するまで”繰り返す
図面上では問題ないと思っていた配置が、現場で見ると違和感がある――ということもよくあります。
そのため、施工前に現場で立って確認する“立体的シミュレーション”や、電気工事士・設計士との綿密なコミュニケーションを重ねることが、後悔を防ぐ最大の手段です。
電気工事は“暮らしの設計図”
新築住宅の電気工事は、「ただ配線を引いて機器をつなぐだけの作業」ではありません。
それは“未来の暮らしを描くための設計図”であり、暮らす人にとって「快適さ」「使いやすさ」「安心感」を形にするための工事なのです。
後悔しないためには――
・ 使用シーンを具体的に想像し
・ プロと何度も打ち合わせをし
・ 将来の変化に柔軟に対応できる工夫を施す
これらを実践することで、電気設備の整った“住み心地の良い家”が完成します。
新築という人生の大きな節目において、電気工事にもこだわりを持って向き合うことが、真に満足できる住まいづくりの鍵になるでしょう。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
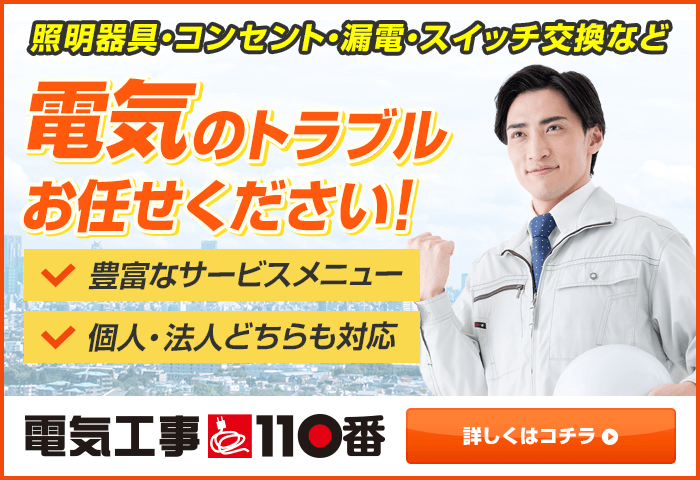
👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
🔽下のリンクから今すぐ『無料相談・見積依頼』が可能です🔽
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
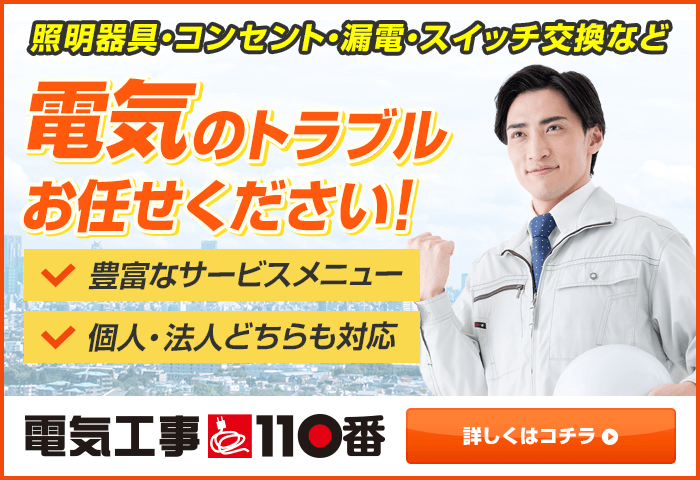
注文住宅・新築住宅での電気工事計画。暮らしやすさを左右する視点とは?
電気工事計画=“暮らし方の可視化”
注文住宅では、自分たちのライフスタイルに合わせて自由に設計できるのが魅力です。しかし、自由度が高い分、施主自身の“判断”が求められる場面も多くなります。その中でも、電気工事は日々の生活をどれだけ快適にできるかに直結する非常に重要な計画要素です。
間取りやデザインと並び、“暮らしやすさを形にする”のが電気計画の本質だと言えるでしょう。
暮らしを見通す4つの視点とは?
1. 「時間帯別の生活動線」を意識する
朝起きてから寝るまで、家の中で人がどう動くか。時間帯別に想定して電源や照明を計画すると、毎日の家事・育児・仕事がスムーズに流れます。
【例】
・ 朝:洗面所にドライヤーとアイロンの同時使用ができる電源容量
・ 昼:リビングでテレワークを行うスペースにLAN+複数電源
・ 夜:ベッドに入りながら調光できる照明スイッチの配置
このように「時間」「人の動き」「使う機器」の3点を照らし合わせて設計することが、暮らしやすさを大きく左右します。
2. 「家族ごとの役割・使い方」に着目する
夫婦・子ども・高齢者といった家族構成や、それぞれの部屋の使い方によっても電気設備の必要量と種類が異なります。
【家族別のニーズ例】
・ 小さな子ども:リビング学習で手元照明+タブレット充電用USBコンセント
・ 高齢者:夜間でも足元を照らす足元灯+人感センサー照明
・ 夫婦:それぞれにスマホ、PC、ドライヤーなどが必要な洗面所や寝室の電源口
つまり、「誰が・どこで・何をするのか」を徹底的に洗い出すことが、満足度の高い電気工事計画の第一歩になります。
3. 「家具配置と干渉しないレイアウト」
意外と多いのが、「設置してから家具と干渉してコンセントが使えなくなった」という失敗です。図面上ではわかりにくくても、家具の奥行き・高さ・配置予定と電源位置を立体的に捉えることで、トラブルを未然に防げます。
特に注意すべきは次の3点です。
・ テレビ背面の電源&アンテナ端子は壁の中央付近に配置
・ ベッドサイドのコンセントはナイトテーブルと干渉しない高さに
・ 冷蔵庫や洗濯機の電源は“差したまま隙間が取れる”位置が理想
4. 「将来的な変化や増設」も前提にする
家は住んでから10年、20年と変化していきます。
子どもが増える、独立する、リフォームする、EVを買う、太陽光を導入する──そんな変化に備えるには、余裕ある配線計画と“アップデート可能な仕組み”を作っておくことが必要です。
具体的には、
・ 各部屋に空配管を通しておく(将来のLANやEV電源に対応)
・ 分電盤の回路数を多めに確保
・ 屋外や外壁に電源ボックスの設置スペースを確保
これらの視点を取り入れることで、新築住宅の「完成度」と「暮らしの満足度」は確実に向上します。

★ 電気工事に関する相談内容ついて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
住宅もオフィスも!電気工事に関する相談の基礎知識と成功の秘訣
電気配線から考える理想の新築住宅設計とは?
見えない場所が「住まいの質」を決める
新築住宅を建てる際、多くの人が重視するのは、目に見える「内装」「設備」「デザイン」です。しかし、住宅の快適性や安全性を根本から支えているのは、“電気配線”という見えないインフラです。
この配線が、計画的に・機能的に・将来性をもって構築されているかどうかで、家の“使い勝手”は大きく変わってきます。電気配線は一度壁や天井の中に隠れてしまうと、簡単には変更できません。
だからこそ、新築時には「今」と「これから」の暮らしに合った配線計画が欠かせないのです。
理想的な配線計画とは?基礎から押さえるべき3つの原則
原則 1:回路は分散・余裕を持たせて設計する
家庭内の電気は、分電盤から各部屋や設備へと回路で分かれて供給されます。この回路が少ないと、1つの回線に電気の負荷が集中し、ブレーカーが頻繁に落ちてしまう原因になります。
【例:リビングだけで必要になる電気機器】
・ エアコン(専用回路推奨)
・ テレビ
・ 照明
・ ゲーム機器やAV機器
・ 加湿器や空気清浄機
・ 掃除ロボット
・ パソコンやスマートスピーカー
このように、リビングだけでも複数の回路を用意すべきなのです。
一般的には、20〜25回路程度が標準とされますが、スマート機器やEV・太陽光発電の導入を考えている場合は30回路以上の設計が望ましいです。また、分電盤自体にも“予備回路”を2〜3口ほど用意しておくことで、将来的な機器追加にも柔軟に対応できます。
原則 2:空配管(先行配管)を活用して「未来」を見据える
電気配線は“固定的”ですが、空配管は“拡張可能な仕組み”です。
空配管とは、あらかじめ壁や天井の中に通しておく「空のパイプ」であり、そこにあとからケーブルやLANを通すことができます。以下のような将来的ニーズに備えるため、空配管を戦略的に配置しておくことが重要です。
【空配管が役立つ場面】
・ 子ども部屋にLANやテレビ配線を追加したいとき
・ 電気自動車(EV)を導入して専用充電器を設置する際
・ 太陽光発電や蓄電池を後から導入するケース
・ スマートホーム機器やセンサー照明の拡張
これらの設備は、10年後に必要になる可能性もあるため、「今は使わないけど、将来のために空配管だけ入れておこう」と考えておくと、リフォーム時に大きな差がつきます。
原則 3:LAN配線・情報系配線も“家電”と同等に扱う
現代の住宅では、照明・エアコン・オーディオだけでなく、通信も“生活必需品”です。Wi-Fiで何でもできると思われがちですが、実際にはLANケーブルでの有線接続のほうが高速かつ安定的です。
【LAN配線のおすすめポイント】
・ 在宅ワークスペース(PC作業やWeb会議用)
・ リビングのテレビ(4K/8K配信・動画視聴)
・ 子ども部屋(オンライン学習やゲーム機)
・ ルーター設置位置からのメッシュWi-Fi拡張の中心位置
さらに、LAN配線と同様に電話線(FAX・固定電話)やインターホン・防犯カメラなどの低電圧配線も同時に計画することで、家全体のネットワークインフラを整えることができます。
配線設計で“やってよかった”と言われる工夫5選
電気工事を実際に行った施主の声をもとに、「やってよかった!」と言われる具体的な工夫を5つ紹介します。
1. TV裏の「壁内配線」でコードすっきり
→ 壁掛けテレビの背面にコンセント・アンテナ端子・LAN端子をまとめて設置
2. 天井裏に通した“将来用の空配管”
→ 太陽光・蓄電池・スマートセキュリティへの追加対応が容易
3. キッチンカウンター下のUSB付きコンセント
→ スマホ・タブレットの充電用に便利で、見た目もスマート
4. 寝室ベッド両脇+ヘッドボード下に調光スイッチ&間接照明
→ 快適な就寝環境とデザイン性を両立
5. Wi-Fi中継機用の天井内配線+コンセント
→ 家中どこでも通信が安定し、見た目もスマート
配線の質が暮らしの“質”を決める
新築住宅における電気配線計画は、「どう電気を届けるか」ではなく、「どう暮らしやすさを届けるか」という視点で考える必要があります。
・ 十分な回路数を確保し、機器ごとに電源を分ける
・ 空配管で将来の拡張性を確保
・ LAN、TV、防犯、スマート家電対応の情報配線も同時に整備
・ 家具配置や生活動線と矛盾のない設計
・ 必要な場所に必要なだけ「電気がある」状態を作る
こうした工夫を一つひとつ積み重ねることで、見えないところまで考え抜かれた“質の高い家”が完成します。
電気配線は、“快適な生活”のための重要な基礎工事です。後悔しないためには、早い段階から配線についてしっかりと考えることが不可欠です。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
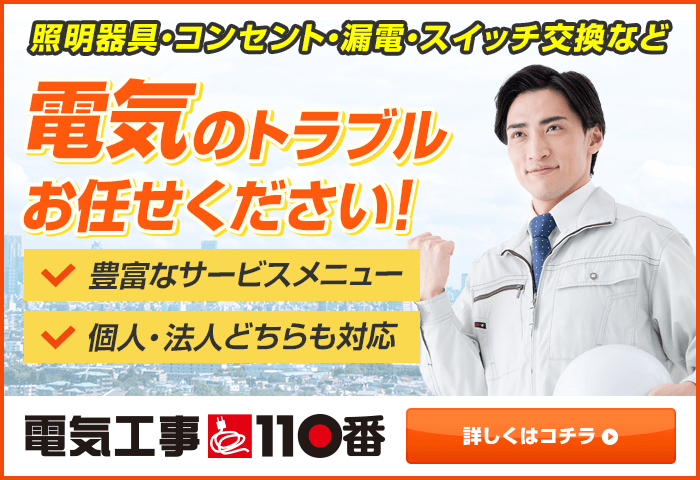

注文住宅・新築住宅で後悔しない!スイッチ・コンセントの配置と電気工事のポイント
「暮らしの流れ」から逆算する設計が成功のカギ
新築住宅におけるスイッチとコンセントの配置は、日々の暮らしをストレスなく過ごせるかどうかを左右する非常に重要なポイントです。
いざ生活が始まってから、「あそこにスイッチがない」「ここにコンセントが欲しかった」と感じる人は少なくありません。それは、図面上では“正しそう”に見える配置が、実際の暮らしに合っていないからです。
だからこそ、電気の配置は動線・用途・生活時間帯を細かくシミュレーションしたうえで決定する必要があります。
スイッチ編:「動きのついでに操作できる」が理想
スイッチの位置は“歩きながら手を伸ばせる”場所に
スイッチの設置で重要なのは、「使うときに迷わず、かつストレスなく操作できること」です。
たとえば、次のような設置が理想的です。
・ 玄関ドアの内側すぐに、廊下とLDKの照明スイッチを設置
→ 帰宅してすぐ点けられることで安心感アップ。
・ 階段の上下どちらにも同じ照明スイッチを設置(3路スイッチ)
→ 上り下りの途中で照明が消せないという不便を回避。
・ 寝室のベッドサイドに主照明+間接照明のスイッチを設置
→ ベッドに入ったあとに立ち上がらずに消灯可能。
スイッチは「ON/OFFの操作性」と同時に、手元の感覚・立ち位置・視認性も大切に設計しましょう。
調光・センサー・スマートスイッチの活用も◎
近年では、調光スイッチや人感センサー付きのスイッチも一般的になっています。
・ トイレや廊下には「人感センサー付き照明」で自動点灯、自動消灯
・ リビングや寝室には「調光スイッチ」で明るさを自由に調節
・ スマートスイッチを使えば「外出先からスマホで消灯操作」も可能
これらの機能は、便利なだけでなく節電効果や安全性の向上にも寄与します。
コンセント編:「足りないより余らせる」が基本スタンス
各部屋でコンセントが不足しがちな箇所と対策
新築住宅で最も多く聞かれるのが「コンセントが足りない」「配置が悪い」といった後悔の声です。
【場所別に見たコンセント不足の“あるある”】
| 場所 | よくある後悔 | 推奨対策 |
|---|
| リビング | テレビ周りがタコ足配線になる | 壁の中央部に6口以上、LAN・TV端子と併設 |
| キッチン | 家電が多く同時使用できない | 冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器はそれぞれ専用回路 |
| 洗面所 | ドライヤー・アイロンが同時に使えない | 2口+追加の高出力対応コンセントを設置 |
| 寝室 | ベッドサイドに電源がない | 左右の枕元+足元に各1口ずつ |
| 廊下・階段 | 掃除機の電源が取れない | 1箇所ごとに1口ずつ設けておくと便利 |
| 子ども部屋 | 成長とともに電子機器が増え、電源が足りなくなる | 壁の上下2段配置(机用・ベッド用)で4口以上 |
家具配置との“バッティング”を避けるには?
家具や家電を置いたあとに「コンセントが隠れてしまった」というのも、多くの家庭で起きているミスです。
対策としては、次の2点が有効です。
・ 図面に“家具の予定配置”を書き込んで電源位置を微調整する
・ 床上30cm、60cm、100cmの高さで配置バリエーションを検討する
とくに冷蔵庫や食器棚、テレビボードのように“動かさない大型家具”は、早めに配置と電源の関係を確定させることが後悔回避の近道です。
さらに満足度を高める+αのアイデア
電気工事をするタイミングで、「やっておけばよかった」と言われがちな+αの工夫も紹介します。
・ 廊下の足元にLED間接照明
→ 夜間でも眩しすぎず、安全性向上
・ クローゼット内にコンセント+照明センサー
→ 暗い収納空間での利便性アップ
・ キッチン床下点検口内に予備電源
→ 食洗機・給湯器・床暖房対応などに活用可能
・ 屋外コンセントを正面と裏手の2箇所以上に設置
→ イルミネーションや洗車、草刈り機などに便利
・ ガレージや駐車場にEV用200Vコンセント+空配管
→ 将来のEV対応も安心
スイッチ・コンセントは“使う瞬間”を徹底シミュレーション
スイッチとコンセントの配置は、設計図だけでは「正解」が見えづらい領域です。だからこそ、実際の生活シーンを頭の中で何度も再現して設計することが何より重要です。
・ どこでスイッチを押すのか?
・ どの家具がどこに置かれるのか?
・ どの時間帯に、どんな電気機器をどこで使うのか?
このようなシミュレーションを元に、将来的な変化や暮らしの進化に対応できる余白のある設計を行うことで、後悔のない「使いやすい家」が完成します。
「もう1口あればよかった」を「この位置にあって助かった」に変えるためにも、スイッチ・コンセントの配置には“暮らし目線”を徹底しましょう。

★ 木造住宅における電気工事について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
木造住宅における電気工事とは?特有の安全対策と施工方法を徹底解説
照明計画も電気工事のうち?注文住宅・新築住宅で差がつく照明設計の工夫
「照明の良し悪し」で住まいの印象は劇的に変わる
注文住宅や新築住宅において、照明は単なる明かりではなく、空間を演出する重要な要素です。
照明が暮らしに与える影響は大きく、
・ 明るさが足りない → 作業効率が落ちる
・ 眩しすぎる → 目が疲れる、リラックスできない
・ 色が冷たすぎる or 暖かすぎる → 空間の印象がチグハグに感じる
このように、照明は身体的・心理的な快適性に直結する存在なのです。
にもかかわらず、配線計画と照明計画を別に考えてしまい、「とりあえずシーリングライトを付けておこう」といった“もったいない照明計画”が後悔の原因になります。照明計画もまた、電気工事の一部として、家の設計段階から“暮らし方”を元に練り上げるべき項目なのです。
「照明=明るくすること」ではない。暮らしの質を上げる“照らし方”の工夫
目的ごとに分けて考える“ゾーニング照明”のすすめ
照明計画は、「明るさの総量」よりも“照らし方の使い分け”が満足度を左右します。
たとえばリビングでは、
・ 食事をするときは明るく
・ 映画を観るときは間接照明で雰囲気良く
・ 来客時は天井全体を照らして印象良く
といったように、ひとつの空間でも用途に応じて照明の種類や配置を変える必要があります。
【ゾーニング照明の組み合わせ例】
| 空間 | メイン照明 | 補助照明 | 装飾照明 |
|---|
| リビング | ダウンライト or シーリング | 間接照明(天井や床) | スポットライトやフロアライト |
| ダイニング | ペンダントライト | 壁付けブラケット | キッチンカウンター下LED |
| 寝室 | シーリングライト | ベッドサイド間接照明 | 調光式読書灯 |
| 玄関・廊下 | 人感センサー付き照明 | 足元灯 | 壁面ディスプレイ灯 |
このように複数の照明を“用途と演出”に応じてレイヤー構成で配置することで、空間に奥行きと快適性が生まれます。
「色温度」「演色性」も見逃せない照明の性能指標
照明器具を選ぶ際には、色温度(ケルビン数)と演色性(Ra値)にも注目しましょう。
・ 色温度(K)
→ 2,700K:暖かみのある色(リラックス向け)
→ 5,000K:昼白色(作業向け)
→ 6,500K:白色光(目が冴える/学習・作業向け)
・ 演色性(Ra)
→ Ra80以上:自然に近い見え方
→ Ra90以上:食材や木目などの発色が美しく見える
特にダイニングやキッチンではRa90以上の照明器具を使うと、食事が美味しそうに見えるなど、快適性だけでなく「視覚的満足感」にもつながります。
照明配置の注意点:「位置」と「高さ」で満足度が決まる
天井だけでなく“壁”や“足元”にも注目
照明の設置と配線は、すべて電気工事に含まれます。だからこそ、配線段階で「ここに間接照明を入れたい」「ここにセンサー付きライトを付けたい」といった細かい希望を伝えておく必要があるのです。
【設置位置と工夫の例】
・ 壁面にピクチャーライトを配置
→ 絵画や観葉植物を美しく演出
・ 床面に足元灯(LED)を配置
→ 夜間の移動時も安全で目に優しい
・ 階段に踏面照明を内蔵
→ 子どもや高齢者の事故防止に効果的
・ トイレや収納に扉開閉連動スイッチ+照明を設置
→ 自動点灯でストレス軽減
このような照明計画は、設計初期に電気工事業者と相談しておかなければ設置が困難になります。また、最近ではダクトレール(ライティングレール)を設置しておくことで、後から自由に照明の配置や種類を変更できる柔軟性も生まれます。
スマート照明と調光・調色の新常識
照明にもIoT化の波が来ています。
スマート照明とは、スマートフォンや音声で操作可能な照明システムで、特に注文住宅では取り入れる方が増えています。
【導入される主なスマート照明機能】
・ アプリで調光や調色ができる
・ タイマー設定で自動ON/OFF
・ 「おはよう」「おやすみ」などの音声コマンドで一括操作
・ 外出先からスマホで操作し防犯対策にも
これらの機能を活用することで、より快適で省エネな暮らしを実現できます。
ただし、スマート照明にはWi-Fi環境やハブ機器、専用スイッチの設置が必要な場合があるため、電気工事業者と早い段階から相談することが必須です。
照明設計は「暮らしの質」をデザインする工程
照明はただの“明かり”ではありません。
・ 快適な生活リズム
・ 心地よい空間演出
・ 作業効率と安全性
・ 家の印象そのもの
これらすべてに影響を与える照明設計は、まさに暮らしを照らす“デザイン”の一部です。
新築住宅において後悔しないためには、
・ 空間の用途ごとに明かりの“質と量”を分ける
・ 間接照明、足元灯、センサーなども設計に取り入れる
・ 色温度、演色性、操作性まで検討する
・ 将来のスマート照明対応も視野に入れる
これらの要素を総合的に計画することで、一歩先を行く“照明で魅せる住まい”が実現します。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
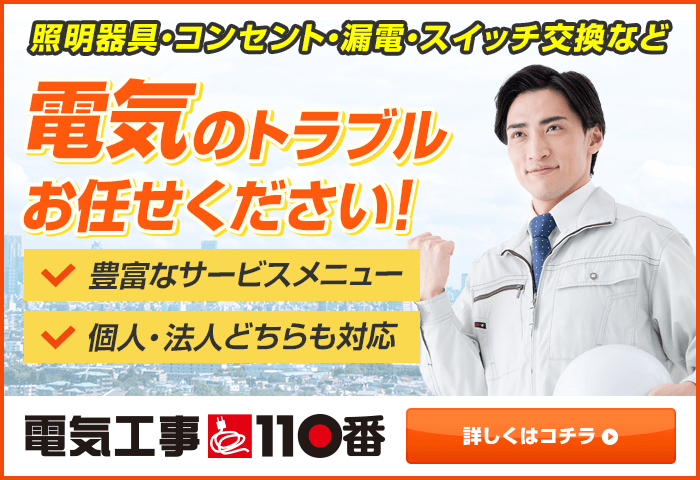

電気工事業者の選び方。注文住宅・新築住宅で安心できる業者を見極めるコツ
電気工事業者は“家づくりの黒子”であり“暮らしの鍵”を握る存在
注文住宅や新築住宅では、設計士や大工、インテリアコーディネーターに目が向きがちです。しかし、日々の快適な暮らしを“目に見えない部分”で支えているのが電気工事業者です。
たとえば──
・ 照明の点灯タイミングが自然であるか
・ スイッチやコンセントの配置が生活動線に合っているか
・ ブレーカーが落ちないように回路分けされているか
・ 将来の機器増設やスマート化に対応できる配線がされているか
これらの要素はすべて、電気工事の「見えない品質」によって決まります。だからこそ、信頼できる電気工事業者を見極めることが、新築住宅の満足度を決定づける重要な要素なのです。
見極めポイント 1:資格・許可を持っているか
電気工事を請け負うには、法的に定められた国家資格と業者登録が必要です。
【確認すべき資格・許可の例】
・ 第二種電気工事士(一般住宅の電気工事に必須)
・ 第一種電気工事士(主に高圧や大規模施設に対応)
・ 電気工事業登録(各都道府県に登録されているか)
・ 工事担任者資格(通信系やLAN工事などに関与する場合)
上記のような資格を保有しているかどうかは、その業者の「技術水準」と「法的信頼性」を示す指標です。また、対応するスタッフ全員が資格を保有しているか、現場での指導体制があるかも確認しましょう。
見極めポイント 2:新築住宅の施工実績が豊富かどうか
一口に電気工事と言っても、その対象はさまざまです。
・ 商業施設のLED化
・ 工場内の高圧設備工事
・ リフォーム住宅の電気更新
・ マンション共用部の通信設備工事
・ そして…新築一戸建ての住宅電気工事
このうち、「新築住宅」の電気工事には特有のノウハウと段取りが必要です。
【新築住宅特有の注意点】
・ 他職種(大工、設備、設計)との施工タイミング調整
・ 施主と直接対話しながら暮らしに合った設計提案
・ 外構やインテリアとの調和を意識した配線、照明設計
・ 法令、地域条例、火災報知設備、分電盤の配置などの対応
過去に何棟以上の新築住宅に携わったか?施工写真や図面はあるか?などを質問し、経験値を確認しましょう。
見極めポイント 3:提案力があるか(“言われた通り”だけで終わらないか)
良い電気工事業者は、単に指示を待つのではなく、施主の暮らしに合わせて“+α”の提案をしてくれます。
【良い提案の具体例】
・ 「お子さんが小さいうちは、ここに夜間照明をつけておきましょうか?」
・ 「ベッドを置く予定でしたら、コンセントの高さを15cm上げておくと便利です。」
・ 「将来的にEV車の導入を想定して、車庫に200V用空配管を通しておきましょうか?」
このように、暮らし方を想像して先回りの提案ができる業者は、本当に住みやすい家を実現するパートナーです。図面にない気付き・暮らしの工夫・リスクの回避まで、“暮らしをデザインできる業者”を選びましょう。
見極めポイント 4:打ち合わせ・現場対応の姿勢
電気工事は、住まいの内部に深く関わる工種です。
そのため、次のような対応の違いが、仕上がりや満足度に大きく影響します。
| 評価軸 | 良い業者の対応 | 悪い業者の例 |
|---|
| ヒアリング力 | 要望の背景まで理解し、提案や代替案を出してくれる | こちらの指示を淡々と受け入れるだけ |
| 対応スピード | 見積・図面・返答が迅速で、連絡も丁寧 | 電話やメールの返答が遅い、曖昧な返事が多い |
| 現場での柔軟性 | 他業者との調整・現場変更にも柔軟に対応 | 「それはできません」「設計通りですから」と突っぱねる |
| コスト意識 | 適正価格で提案し、オプションの費用も明確に説明してくれる | 「一式」「詳細不明の追加料金」など曖昧な見積 |
安心して任せられる業者は、説明が丁寧でコミュニケーションが的確です。
確認すべき質問集:電気工事業者との打ち合わせで使える実践フレーズ
以下は、電気工事業者との打ち合わせで役立つ“実際の質問例”です。
・ 「新築住宅の施工実績はどれくらいありますか?」
・ 「間接照明を使いたいのですが、施工事例はありますか?」
・ 「LANやスマートホーム対応の配線はできますか?」
・ 「後から照明やコンセントを増やす場合、空配管は必要ですか?」
・ 「保証内容やアフター対応はどうなっていますか?」
・ 「分電盤の回路数は今後の増設に対応できるよう設計できますか?」
これらの質問を通じて、業者の知識・経験・対応力を見極める材料にしましょう。
できる業者は“暮らしの設計者”
電気工事は、単なる「設備設置」ではなく、あなたの生活を形にする重要な設計・施工工程です。
・ 技術力
・ 提案力
・ 経験値
・ 対応力
この4点を備えた業者こそが、後悔のない注文住宅を完成させるための最重要パートナーとなります。価格の安さや見た目だけで判断せず、一緒に暮らしをつくるという視点で業者選びを行いましょう。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
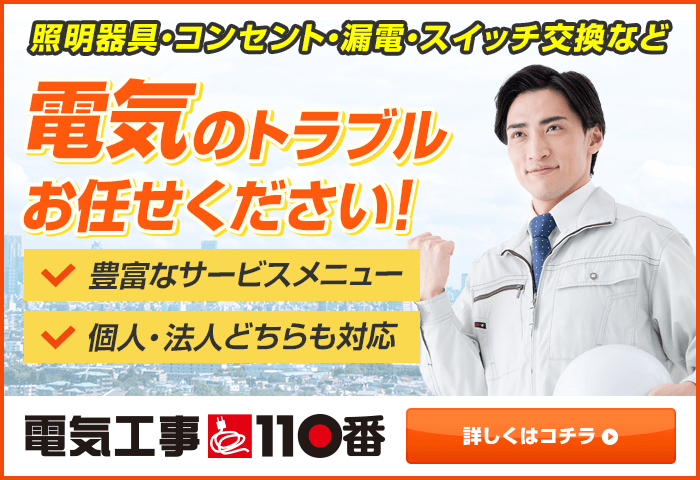

スマートホーム対応もお任せ!注文住宅・新築住宅の電気工事最新事情とは?
住宅は今、“スマート化”という大きな進化の時代へ
ここ数年で、住宅に求められる役割が大きく変わりつつあります。
従来の家は「住む場所」であり、「電気」は照明・家電の動力源として使われていました。しかし今では、インターネットと連携する“スマートホーム”という概念が主流になりつつあり、電気工事もまたその流れに対応する形で進化しています。
スマートホームとは、IoT(Internet of Things)機器を住宅に組み込み、電気・通信・制御を連動させて快適な生活を実現する仕組みです。照明・エアコン・カーテン・ドアロック・カメラ・給湯器など、家中の機器をアプリや音声、スケジュールで自在に操作できるスマート住宅は、今や「高級住宅」の専売特許ではありません。
新築の時点で設計・配線を整えておけば、手軽にスマートホーム化を実現することが可能です。
スマートホーム化に必要な「電気工事の準備」とは?
1. 専用配線・LAN環境の整備
多くのスマート機器はWi-Fiで操作されるものの、中核となる通信機器や制御装置には有線LANや電源が必要です。
【よくある電気工事対応項目】
・ ルーター周辺に集中配線盤+有線LANケーブル
・ スマート照明用に専用スイッチ+中継器の設置スペース
・ 屋外カメラ用に防水型電源コンセント+PoE対応LAN
・ 太陽光、HEMS、蓄電池の連携には制御盤への接続工事
スマートホーム化を本格的に進めたい場合、情報配線は電気配線と同等レベルの重要性を持ちます。
2. スマート照明・スマートスイッチの導入
現在主流のスマート照明には、以下のような機能があります。
| 機能 | 具体的な内容 |
|---|
| 調光・調色 | 明るさと色温度をスマホアプリで自由に調整 |
| 音声操作 | AlexaやGoogle Homeと連携し声でON/OFF操作 |
| スケジュールタイマー | 就寝時間に自動でOFF/朝起床時に徐々に点灯 |
| グルーピング操作 | 部屋単位・用途単位で複数照明をまとめて一括制御 |
これらを導入するには、対応するスイッチ・中継器・制御アプリに合わせた電気配線設計が必要です。また、調光スイッチを使う場合は、照明器具側も調光対応である必要があるため、機器選定と施工計画をセットで考えることが必須です。
3. スマートロック・セキュリティ対応の電源確保
玄関ドアや勝手口に設置されるスマートロック・インターホン・防犯カメラ・人感センサー照明などにも電源供給が必要です。
【注意点】
・ 屋外設置のスマート機器には防水や耐候性の高い屋外用コンセントが必須
・ 中継器や親機が宅内に設置される場合は床上100cm前後に配線口やLAN口を設ける
・ 24時間稼働するため、ブレーカーとは別の“常時通電回路”を設ける配慮があると安心
これらの対策は、後から行おうとすると壁や外壁の穴開け・再配線といった大掛かりな工事が必要になるため、新築時に盛り込んでおくのが圧倒的に効率的です。
最新のスマート住宅でできること 【実例紹介】
CASE1:共働き家庭のスマートライフ
・ 外出先からスマホでエアコンを起動して帰宅時に快適室温
・ 宅配ボックスと連動したスマートインターホンで荷物の受け取り通知
・ スケジュールで照明が自動でON/OFF、夜間の不在時も防犯効果UP
CASE2:子育て世帯の安心・快適な住環境
・ 寝室に設置した人感センサーで、夜間に自動で足元灯が点灯
・ 子どもが留守番中でも、スマートカメラで外出先から状況を確認
・ ベビールームの照明と空調をスマホから一括管理
CASE3:高齢の両親との同居住宅
・ 音声操作による照明やカーテンの開閉で生活の自立支援
・ スマート照明による転倒防止
・ センサーで異常を検知した際はスマホに即通知
これらの実現には、“どの機器を使いたいか”を電気工事の段階で明確にしておくことがポイントです。
スマートホーム対応の電気工事で失敗しないための注意点
1. 機器選定を早い段階で行う
→ スマート機器には“設置条件”や“配線要件”があるため、設計時点で業者と共有が必須。
2. Wi-Fi・LANの電波強度にも配慮する
→ 中継機やメッシュWi-Fiの導入計画とセットで考えること。
3. 対応できる電気工事業者を選ぶ
→ IoTやスマートホームに詳しい業者でなければ施工トラブルが起きやすい。
4. メーカー推奨の構成や設置場所に従う
→ 仕様と異なる設置をすると、保証対象外になることもある。
スマートホームは“暮らしを再発明する”設備計画
スマートホーム対応の電気工事は、もはや「オプション」ではなく、“これからのスタンダード”です。
・ 自動で照明や空調をコントロール
・ 外出先から防犯や生活機器をチェック
・ 音声やスマホで住宅を操作
・ 電気代の“見える化”で省エネにつながる
これらの仕組みは、生活の安心・快適・効率化を劇的に変えてくれます。
注文住宅だからこそ、新築の段階で“配線・電源・通信インフラ”をしっかりと整備し、「今だけでなく未来にも対応できる住宅」を目指すことが、後悔のない住まいづくりの鍵です。

★ 新築住宅におけるLAN配線の必要性について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
新築住宅にLAN配線は必須?その理由とメリットを徹底解説
まとめ
「電気工事」こそ、暮らしの快適性を支える“目に見えない設計”
注文住宅・新築住宅の設計において、間取りやインテリアのような“見える部分”に注目が集まりがちですが、実はその裏側で家の快適性を支えているのが、電気工事という“見えないインフラ”です。
電気工事は、単に「コンセントを付ける」「照明を点ける」という作業にとどまりません。それは、家の中でどこで何をするか、いつ、どのように動くかという生活のすべてを支える“暮らしの設計”そのものです。
この重要な工程を適切に計画・実行することで、住宅の住み心地・安全性・利便性は格段に向上します。
各セクションから見えてきた“後悔しないための鉄則”
本記事では、注文住宅・新築住宅の電気工事について、以下の視点から詳しく掘り下げてきました。
1. 電気工事の基本理解
電気工事は設計段階から密接に関わるべき工程であり、後から変更が難しいからこそ、最初の段階で生活に合った設備を“予測”しておくことが鍵になります。
2. 生活動線からの逆算設計
コンセントやスイッチの配置は、「生活の流れ」を基にして考えることで、日常のストレスを限りなくゼロに近づけることが可能です。
3. 配線設計と将来対応力
空配管・予備配線・多回路分電盤などを導入することで、将来的なリフォーム・EV導入・スマートホーム化にも柔軟に対応できる設計が可能になります。
4. 照明計画の重要性
“明るさ”ではなく“照らし方”にこだわることで、空間の印象と機能性を大きく向上させることができます。照明は空間を演出するデザインの一部です。
5. 業者選びの基準
電気工事業者は、資格・実績・提案力・対応力で選びましょう。「暮らしを設計できる人材かどうか」が選定の最大ポイントです。
6. スマートホーム対応
最新の住宅では、電気設備と通信設備が一体となったスマート化が進んでいます。最初の段階から対応を見据えた設計が求められる時代です。
チェックリスト:電気工事で後悔しないために設計段階で確認したい10項目
| チェック項目 | 内容 |
|---|
| コンセントの数・位置 | 各部屋の生活動線・家具配置に応じて最適な数と場所か? |
| スイッチの配置 | 生活動作の“ついで”で操作できる位置にあるか? |
| 回路設計 | 使用する機器ごとに電源回路が分かれているか? |
| 空配管・将来対応 | 将来的な追加機器の配線に対応できる余裕があるか? |
| LAN・テレビ・通信機器の配線 | 有線通信が必要な部屋・機器に対応しているか? |
| 照明計画 | 用途ごとに照明の種類・明るさ・演出が設計されているか? |
| 調光・センサー・スマート照明への対応 | 最新機器に対応した照明設計・制御機器が導入されているか? |
| 屋外配線(防犯・EV・照明) | 外構・車庫・防犯用に十分な電源と配線が設計されているか? |
| 分電盤の回路数・拡張性 | 将来的な電力需要にも対応できるよう余裕を持たせて設計しているか? |
| 業者の提案力・対応力 | 暮らしに合わせた提案や、柔軟な打ち合わせを行ってくれる業者かどうか? |
このチェックリストを元に打ち合わせを進めれば、電気工事での「しまった…」を確実に減らすことができます。
「一生に一度の住まいづくり」だからこそ、電気にも徹底的にこだわるべき
多くの人にとって、新築住宅を建てるのは一生に一度の大きなプロジェクトです。だからこそ、見た目や構造だけでなく、見えない“電気”の部分にもとことんこだわることが、快適な住まいづくりを成功させる秘訣になります。
電気工事は、建物が完成したあとには変更しづらい部分だからこそ、最初から「暮らしをイメージして設計する姿勢」が問われます。
・ 日常の何気ない動作
・ 家族のライフスタイル
・ 将来のライフステージの変化
・ そして、テクノロジーの進化
こうしたすべてに対応するためには、“今だけでなく未来まで見据えた電気設計”が求められる時代です。
最後に
あなたの新築住宅が、「ただ住む場所」ではなく「毎日が快適で、安心できて、将来まで柔軟に対応できる住まい」になるように、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
電気工事のことまで真剣に考えた家は、住み始めたその日から、“選んで良かった”と実感できるはずです。
そして、そうした家こそが、本当の意味で“理想の住まい”と言えるのではないでしょうか。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼