
犬によるLANケーブル断線は意外と多い?
実際のトラブル事例
近年、「インターネットが突然つながらなくなった」「通信速度が極端に遅くなった」という相談の中で、“原因は犬によるLANケーブルの断線だった”というケースが非常に多く報告されています。
特に犬を飼っている家庭では、LANケーブルが床を這っている構造が多く、犬の目線や口の高さにちょうど合ってしまうことが大きな要因です。
実際にあったトラブルとして、次のような事例が見られます。
事例 1:留守番中の子犬がLANケーブルを噛みちぎったケース
飼い主が外出中に、ケージの外で遊んでいた子犬がLANケーブルをおもちゃ代わりに噛み続けた結果、完全に断線。
帰宅後に「Wi-Fiがつながらない」と気づき、確認してみるとケーブルが真っ二つに切れていたという典型的なパターンです。
被膜が破れて内部の銅線が露出しており、ショートや感電の危険性も伴う非常に危険な状態でした。
事例 2:見た目は無事なのに通信が不安定
一見ケーブルが無傷のように見えても、犬の歯による微細な傷や折れが内部導線を断線させる場合があります。
この場合、通信が断続的に切れる・速度が低下する・ルーターランプが点滅を繰り返すなど、「原因不明の接続不良」として現れることが多く、発見が遅れるのが特徴です。
最終的に電気工事業者がケーブルテスターで調べたところ、ケーブル中央部で信号が途切れていたという事例もあります。
事例 3:犬の誤飲による二次被害
LANケーブルの被膜は柔らかく、噛みやすいため、犬が誤って断片を飲み込んでしまうケースも報告されています。
この場合、腸閉塞や消化器損傷など、命に関わる事態に発展することもあるため要注意です。
実際に動物病院で「LANケーブルのビニール片を飲み込んだ」と診断された例もあり、ネットのトラブルどころかペットの健康被害にまで及ぶ深刻な問題です。
こうしたトラブルの特徴は、「最初は小さな傷」から始まり、気づかないうちに重大な断線や危険につながるという点です。
つまり、LANケーブルの断線は一瞬の事故ではなく、日常的な「噛み癖」や「環境要因」によって進行するリスクなのです。
特に、LANケーブルが床に露出していたり、ルーターからパソコン・テレビへの配線が壁際に通っていたりすると、犬の行動範囲に入りやすくなります。
犬は柔らかいものや動くものに興味を示すため、ケーブルを“遊び道具”や“獲物”と誤認してかじることが多いのです。
また、LANケーブルは細くて電流が弱いため、噛んでもすぐに電気的な痛みを感じにくいという点も問題を悪化させます。
電源コードのように「ビリッ」とならないため、犬が学習しにくく、繰り返し噛む習慣が定着しやすいのです。
結果として、
・ 通信不良やネット接続トラブル
・ 火災やショートの危険性
・ ペットの誤飲、感電事故
という三重のリスクが同時に存在します。
したがって、犬を飼っている家庭では、LANケーブルの位置や種類、配線方法を工夫することが極めて重要です。
「ケーブルを見せない・触れさせない・噛ませない」という3つの原則を意識するだけで、これらのトラブルは大幅に減らせます。
このように、犬によるLANケーブル断線は決して珍しい出来事ではなく、「どの家庭にも起こり得る日常的なトラブル」として認識しておく必要があります。
特に子犬期や留守番が多い環境では、事前の対策と定期的な点検が、愛犬とネット環境の両方を守るカギになるのです。
▼ LAN配線に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番> ▼
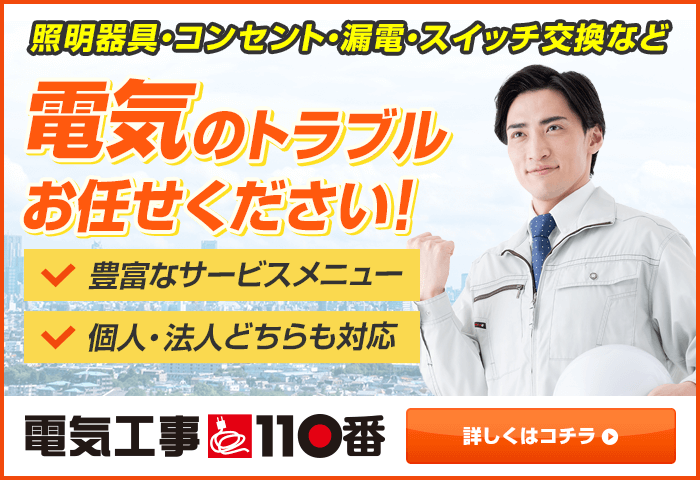
👉 LAN配線でネットが快適に!通信トラブルを防ぐなら【電気工事110番】にお任せ
現代の生活において、インターネットは水道や電気と同じくらい欠かせない存在となりました。動画配信、リモートワーク、オンライン授業、IoT家電の利用など、安定した通信環境が日常に直結しています。しかし、意外と見落とされがちなのが「LAN配線の品質」です。
「Wi-Fiが不安定」「通信速度が遅い」「会議中に音声が途切れる」…そんなお悩みを抱えている方は、ぜひLAN配線の見直しを検討してみてください。そして、その工事を信頼できるプロに任せるなら、【電気工事110番】が圧倒的におすすめです。
なぜLAN配線が重要なのか?通信トラブルの多くは“配線”が原因
多くのご家庭やオフィスでは、Wi-Fiルーターのスペックや通信プランばかりに注目しがちですが、「LAN配線の劣化」や「不適切な配線方法」が原因で通信速度が落ちているケースも少なくありません。
よくあるLAN配線のトラブル事例
・ 築年数の経った住宅で使用されている古いLANケーブル
・ 天井裏や床下での断線・接触不良
・ 無理な分岐や延長による信号劣化
・ 外部ノイズによる通信エラー(特に電源ケーブルと並行に配線されている場合)
こういった問題は、通信機器をいくら高性能にしても解決できません。根本から快適な通信環境を整えるには、適切なLAN配線工事が必要不可欠です。
LAN配線を見直すメリットとは?
LAN配線工事をプロに依頼して改善すると、以下のようなメリットがあります
✅ 通信速度の向上:光回線本来のスピードを最大限に引き出せる
✅ Wi-Fiの安定化:メッシュWi-Fiやアクセスポイントとの相性も◎
✅ 業務効率アップ:オンライン会議やクラウド業務がスムーズに
✅ 防犯カメラやIoT機器との連携が快適に
✅ 将来の回線増設やリフォーム時の拡張性も確保
「電気工事110番」のLAN配線サービスが選ばれる理由
LAN工事は、単にケーブルを通すだけではなく、建物構造や配線経路、ネットワーク機器との整合性を熟知したプロの知識が求められます。
「電気工事110番」は、全国対応・最短即日対応可能なうえ、以下のような安心の特徴を持っています。
| 特徴 | 内容 |
|---|
| ✅ 明朗な料金体系 | 事前見積で追加費用なし(※現地調査あり) |
| ✅ 全国対応 | 都市部から地方まで対応可能 |
| ✅ 年中無休・24時間受付 | 急なトラブルにもスピーディに対応 |
| ✅ 有資格者による施工 | 電気工事士資格を持つプロが対応 |
| ✅ 累計相談実績30万件以上 | 多くのユーザーから高評価 |
LAN配線工事の具体例:こんなシーンで活用されています
戸建て住宅
・ リビング、書斎、子供部屋にLANを分配して快適ネット環境を構築
・ 防犯カメラのPoE接続やNAS設置にも対応
賃貸マンション
・ 原状回復に配慮した露出型モール工事
・ Wi-Fiの届かない部屋への有線接続
オフィス・店舗
・ 社内ネットワークの設計、配線、ハブ設置まで一括対応
・ POSレジや監視カメラの安定接続工事も
LAN配線はプロに任せて、安心・快適な通信環境を!
通信トラブルの原因がWi-Fiや回線プランではなく、「LAN配線の問題」だったという事例は少なくありません。正しく配線された有線LAN環境こそが、真に安定したネットワークの基盤となります。
「LAN配線工事をプロに任せたい」「どこに相談すればいいか分からない」――そんなときは、「電気工事110番」にご相談ください。
👇 下のリンクから『無料相談・見積依頼』が可能です / 今すぐチェックを!!
▼ LAN配線に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番> ▼
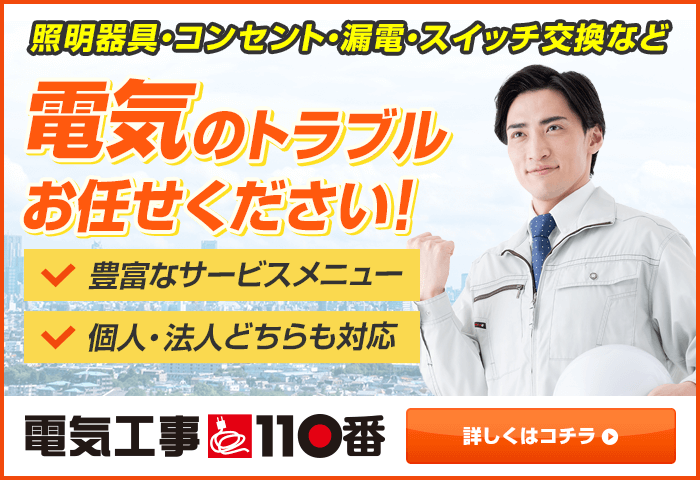
犬がLANケーブルをかじる3つの主な原因
LANケーブルの断線トラブルを根本から防ぐためには、「なぜ犬がLANケーブルを噛むのか」という原因を正しく理解することが不可欠です。
犬がLANケーブルをかじる行動には、単なるいたずらではない、本能的・心理的・生理的な理由が隠れています。
以下では、その主な原因を3つに分けて詳しく解説します。
1. 好奇心と探索本能による「遊び行動」
犬がLANケーブルをかじる最大の理由は、好奇心と探索本能です。
特に子犬期や若い犬は、身の回りのものを口で確認する習性があり、家具や布、電気コードなどを“噛んで確かめる”行動を取ります。
LANケーブルはその形状から、犬にとって「動く紐」や「細長いおもちゃ」に見えます。
人がケーブルを動かしたり掃除機をかけたりする際に少し揺れるだけでも、犬の狩猟本能を刺激してしまうのです。
つまり、LANケーブルは犬にとって“動くターゲット”に見えるため、噛んで遊ぶ行動が自然と起こります。
また、LANケーブルの素材(PVCやナイロン被覆)は弾力があり、噛んだときに「プチッ」という音や感触が得られます。
この“感触の快感”が学習されると、習慣的にケーブルを狙う行動が定着します。
実際に多くの飼い主が「一度噛んでから何度も同じ場所を狙うようになった」と報告しています。
特に、床に這わせたLANケーブルやルーター周辺の露出配線は、犬の目線の高さにあるため格好の標的になります。
この場合、“犬が届かない位置にケーブルを移動する”ことが最も効果的な対策です。
2. ストレスや退屈による「破壊衝動」
犬がLANケーブルを噛む2つ目の原因は、ストレス・退屈感・不安感です。
特に留守番の時間が長かったり、運動不足の犬は、ストレスを発散するために「破壊行動」を取ることがあります。
この行動は、飼い主の注意を引くためのアピールとしても現れます。
たとえば、「ケーブルを噛むと飼い主が慌てる」という学習が起きると、犬は構ってもらう目的で繰り返すようになります。
結果として、LANケーブルが“噛む=飼い主が反応する”という誤学習が強化され、行動が固定化してしまうのです。
また、特に梅雨や夏季など外出時間が減る時期には、運動不足と退屈が重なって破壊行動が増える傾向があります。
LANケーブルは細くて柔らかいため、家具や金属よりも噛みやすく、犬にとってストレス発散の対象として選ばれやすいのです。
このようなケースでは、環境調整が非常に重要です。
・ 留守番時に安全なおもちゃを与える
・ 噛む専用ガムやデンタルトイを用意する
・ 散歩や遊びの時間を増やす
といった日常的な工夫で、LANケーブル被害を大幅に減らすことができます。
特に、“噛んではいけないもの”を叱るより、“噛んでいいもの”を与えるほうが学習効果が高く、長期的に安定します。
3. 歯の生え変わり期や口腔違和感による「生理的要因」
3つ目の原因は、歯の成長や口内の違和感です。
生後3〜6ヶ月の子犬は乳歯から永久歯に生え変わる時期であり、この期間は歯ぐきがむずがゆく、自然に何かを噛みたい衝動が強くなる傾向があります。
LANケーブルの外皮は柔軟で弾力があり、噛むことで痛みやかゆみを軽減できるため、犬にとって「ちょうど良い噛み心地」に感じられてしまうのです。
特にこの時期は、家具の角・スリッパ・布製クッションなども被害を受けやすく、LANケーブルも例外ではありません。
さらに、シニア犬の場合も油断は禁物です。
加齢によって歯の不快感や歯石、口内炎が生じると、無意識に硬いものを噛んで違和感を解消しようとする行動を取ることがあります。
このような生理的要因が絡む場合、単なる行動矯正だけでなく、獣医師による口腔チェックも併せて行うことが効果的です。
【犬がLANケーブルを噛む3つの主要原因と特徴】
| 原因分類 | 行動の背景 | 典型的な犬の様子 | 主な対策 |
|---|
| 好奇心・探索本能 | 新しい物・動く物に興味 | ケーブルを観察しながら口にくわえる | ケーブルを隠す・固定する |
| ストレス・退屈 | 留守番・運動不足・寂しさ | 飼い主の不在時に噛む・壊す | 遊び・運動量を増やす・防噛グッズ |
| 生理的要因 | 歯ぐきのむずがゆさ・口内違和感 | 若齢犬・高齢犬に多い | デンタルケア・噛み心地の良いおもちゃを用意 |
このように、LANケーブルをかじる行動は一見いたずらに見えても、犬の心理や健康状態と深く関係しているのです。
したがって、単純に「叱る」「スプレーをかける」といった一時的な対処ではなく、犬の行動の背景を理解し、根本から環境を改善することが重要です。
LANケーブルを保護することは、単なる機器トラブル防止にとどまらず、犬の安全と快適な生活を守るための愛護的対策でもあります。

★ 猫によるLANケーブルのトラブルについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
LANケーブルを猫が噛んでボロボロに?対策と安全な配線設計











