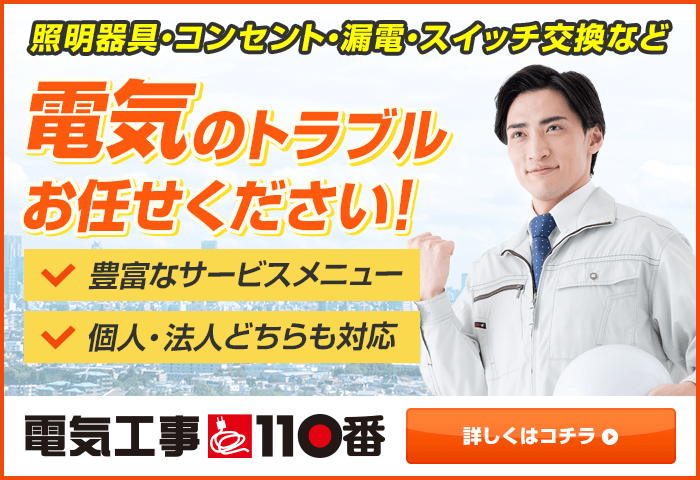空調工事における電気工事って何?
「空気を整える」ために必要な“電気の土台づくり”
空調工事における電気工事とは、エアコンや換気扇、送風機などの空調機器を安全かつ確実に動作させるための電力供給・制御・保護を目的とした工事を指します。エアコン1台を取り付けるだけでも、電気が安定して供給されなければ冷暖房の機能はまったく果たせません。
たとえば、住宅用のルームエアコンであっても、「100V/200Vいずれが必要か」「専用回路は確保されているか」「アースは取れているか」など、電源環境に関する要件は必ず確認すべきポイントです。これらを整えるために行われるのが、電源ケーブルの配線工事や分電盤からの回路引き込み、ブレーカーやコンセントの設置工事です。
また、空調機器は長時間稼働し続ける性質があるため、過電流や漏電が発生した際に即時遮断できるような安全装置の設置(漏電ブレーカーやアース工事)も重要です。
こうした工事のすべてが、法令で定められた「電気工事士」資格を有する者によって行わなければならない作業に該当します。
【代表的な電気工事の内容】 空調工事との関連で
| 作業項目 | 内容の説明 |
|---|
| 専用回路の設置 | 高出力の空調機器に必要な個別の回路を分電盤から引く |
| コンセントの増設・切替 | 機器の仕様に応じて100V→200Vの切替や屋外対応の防水コンセントの施工など |
| ブレーカーの増設・容量変更 | 機器の定格消費電力に応じて安全に動作させるための過電流保護装置の設定 |
| アース・漏電遮断器の設置 | 感電や漏電火災の防止を目的とした保安工事。法令上必要なケースが多い |
| 制御回路・リモコンの接続 | 温度制御・タイマー・遠隔操作などを行うための信号配線 |
こうした作業を適切に行うことで、機器の寿命が延び、トラブルの発生も最小限に抑えることができるのです。
家庭でも、オフィスでも、工場でも求められる「電気的知見」
空調機器の規模や用途によって、求められる電気工事の内容は大きく異なります。
たとえば、一般家庭であれば単相100Vまたは200Vのコンセント設置が主な作業ですが、事務所や工場、店舗などでは三相200Vの動力回路の整備が必要になります。また、建物の構造(鉄筋コンクリート造/木造)や既存の配線状況によって、配線経路の確保や施工方法も変わってくるため、現地調査の段階から電気工事士の判断が重要となります。
さらに近年では、空調と電気工事がIoT化・スマート化によってより密接に関わるようになってきました。
スマートリモコンやHEMS(Home Energy Management System)と連携させる場合、単なる電源工事に加え、通信ネットワークとの調整や制御信号の分岐など、電気通信工事に近い技術が必要とされるケースも増えています。
電気工事は「裏方」ではない、空調機器の性能を左右する鍵
空調機器の性能や設置工事の精度がどれほど高くても、電気の供給が不安定だったり安全対策が不十分だったりすれば、機器は正しく作動せず、故障や事故のリスクを高めることになります。そのため、「空調工事の一部にすぎない」と軽視されがちな電気工事こそが、空調設備を快適・安全・長寿命で使うための根本的なインフラなのです。
つまり、空調工事における電気工事とは、機器を支える“電気の土台”を築く極めて重要な工程であり、その質が空調設備全体のパフォーマンスを決定づけるといっても過言ではありません。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
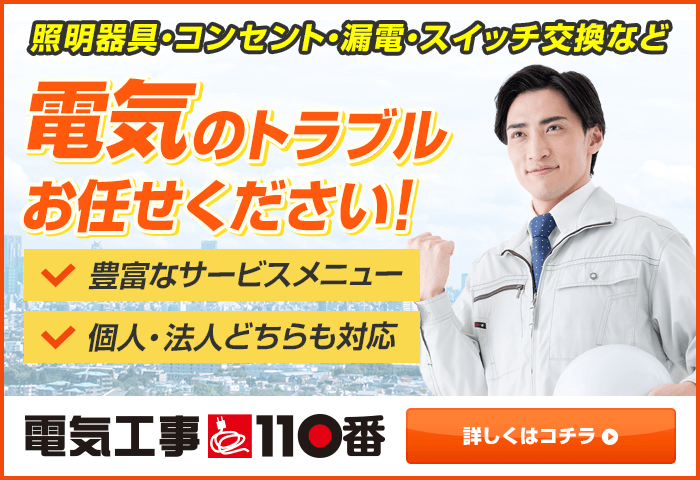
👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
🔽下のリンクから今すぐ『無料相談・見積依頼』が可能です🔽
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
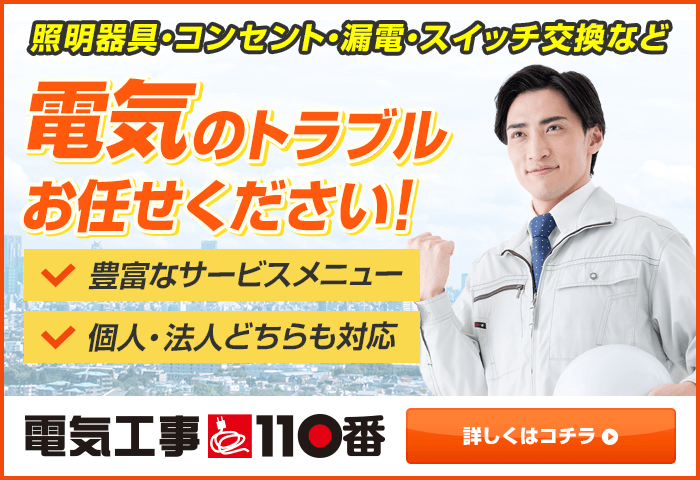
電気工事と空調工事ってどんな関係性なの?
表裏一体の技術領域──“設備”と“インフラ”の切っても切れない関係
空調工事と電気工事は、それぞれ異なる分野で専門性を持つ作業ですが、現場においては密接不可分な関係性にあります。空調工事が「空気の流れをつくる設備の設置」であるとすれば、電気工事はその設備を「動かすためのエネルギー環境を整える工事」です。
つまり、空調と電気は“設備”と“インフラ”の関係にあり、片方が欠ければ機能は成立しません。
特に業務用空調システムや高機能住宅においては、空調機器が多機能化・大型化しており、電気的な要求も高度化しています。このため、電気工事の品質や設計内容が、空調機器の性能を左右する要素となっているのです。
【空調工事と電気工事の具体的な連携例】
| 工事場面 | 空調工事の内容 | 電気工事の内容 |
|---|
| 一般住宅でのルームエアコン設置 | 室内機・室外機の取り付け、配管敷設 | 専用回路の新設、200Vコンセント増設、アース接続 |
| オフィスでの業務用エアコン導入 | 天井カセット型エアコンの設置、冷媒配管処理 | 三相200Vの動力回路施工、分電盤容量の見直し |
| 工場での集中空調システム施工 | 吹出口・ダクト・ゾーン分け設計 | 監視制御盤との接続、タイマー制御、ネットワーク配線設計 |
こうして見ると、空調機器の設置場所、用途、規模が変わるたびに、電気工事の内容も比例して複雑になることがわかります。
連携が取れていないとトラブルの原因に
空調工事と電気工事の連携がうまくいっていない場合、施工時点では問題がないように見えても、運用開始後に大きな支障が出ることがあります。
たとえば、以下のようなケースが実際の現場で報告されています。
【よくあるトラブル例】
・ 空調機器の起動時にブレーカーが落ちる
→ 電源容量の計算が不十分で、空調起動時の突入電流に対応できていなかった。
・ 冷房中にコンセントが熱を帯びる
→ 専用回路ではなく、他の家電と同一回路に接続されていたため、過負荷が発生。
・ リモコン操作が効かない、誤動作する
→ 制御信号線の誤配線や、絶縁処理不良が原因でリレー回路が誤作動。
これらは、いずれも空調工事側と電気工事側が連携不足で、設計段階での調整がなされていなかったことが主な原因です。そのため、空調設備の導入や更新時には「空調と電気を一体で考える」という設計思想が欠かせません。
現場で求められる“ハイブリッドな対応力”
近年、空調設備と電気設備の融合が進む中で、現場では空調と電気の両方に精通した対応力が強く求められています。とくに中小規模のリフォームや店舗の新装工事などでは、「空調も電気も一括で対応してくれる業者が欲しい」というニーズが非常に高まっているのが現実です。
その背景には、以下のような要因があります。
・ 分離発注による管理コストの増大
・ 施工工程の複雑化による日程の調整難
・ 工事範囲の境界が曖昧で、トラブルが起きやすい
こうした課題を解消するために、電気工事士の資格を持つ空調技術者や、空調施工にも精通した電気工事業者の存在が重要視されるようになっています。
今後は、空調と電気の知識を併せ持った“クロスジャンル型技術者”の育成が、業界全体の発展にも大きく寄与していくでしょう。
設計段階から「電気と空調の融合」を前提とすべき時代へ
これまで、空調工事と電気工事は分業が当たり前とされてきました。しかし現在では、設計段階から両者を一体的に捉え、建物のインフラ全体を最適化するアプローチが求められるようになってきました。
たとえば、BEMS(ビルエネルギー管理システム)やHEMS(家庭用エネルギー管理システム)などにおいては、空調・照明・動力・給湯などの消費電力を一元的に監視・制御する設計がスタンダードになりつつあります。
このような状況下では、空調と電気の境界はますます曖昧になり、「どちらの業者がやるのか」よりも「誰が全体を理解しているのか」が重視される時代になるといえるでしょう。

★ 空調設備に関連する内容についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
電気設備と機械設備の違いとは?それぞれの役割と運用における重要性
エアコン工事って電気工事なの?
結論:一部は明確に“電気工事”に該当します
エアコン工事と聞くと、多くの方が「本体を壁に取り付けて、配管を通して終わり」といった簡単な作業をイメージするかもしれません。しかし実際には、エアコンの設置には多くの“電気的作業”が含まれており、その一部は法令で「電気工事」に区分されています。
具体的には、以下のような作業が該当します。
・ 専用回路の新設(分電盤からエアコンまでの電源引き込み)
・ 電圧切替(100Vから200Vへの変更)
・ アース工事(感電、漏電事故を防止)
・ ブレーカーの設置または増設
・ 配線の接続(機器と電源を直接つなぐ)
これらは、電気工事士の資格を持たない人が施工すると法律違反になるだけでなく、火災や感電など重大な事故を引き起こす原因になります。
そのため、エアコンの設置に関しても、「どの範囲が電気工事に該当するのか」を明確に把握し、適切な業者に依頼することが非常に重要です。
【エアコン工事の中で電気工事にあたる作業】
以下に、エアコン設置における主な作業と、その分類を表にまとめました。
| 作業内容 | 工事分類 | 資格の有無が必要か |
|---|
| 室内機・室外機の取り付け | 空調工事 | 不要(経験は必要) |
| 冷媒配管の敷設・真空引き処理 | 空調工事 | 不要(技術は必要) |
| 室内外の電源ケーブルの接続 | 電気工事 | 必要(電気工事士) |
| 専用回路の新設・電圧変更 | 電気工事 | 必要(電気工事士) |
| コンセントの交換または新設 | 電気工事 | 必要(電気工事士) |
| アース端子の接地 | 電気工事 | 必要(電気工事士) |
| ブレーカーの取付や増設 | 電気工事 | 必要(電気工事士) |
つまり、“壁に取り付ける作業”以外の多くが電気工事に該当するというのが現状です。
「自分でできそう」は危険!DIY設置のリスクとは?
近年、ネット通販などで安価にエアコン本体を購入できることから、「自分で取り付けたい」と考える人も少なくありません。
しかし、エアコンの設置には以下のようなリスクが存在します。
【DIY設置の主なリスク】
・ 漏電や感電による人身事故
・ 過電流によるブレーカー作動や火災
・ 冷媒ガスの漏れや機器破損による故障
・ 建物の配線基準違反による法令違反
・ メーカー保証の無効化(無資格施工による)
これらのリスクを避けるためにも、電気工事士の有資格者が在籍する専門業者に依頼することが、安全性と品質確保のための最低条件といえるでしょう。
実際には“空調工事と電気工事の組み合わせ”が必要
ほとんどのエアコン設置現場では、空調工事と電気工事の両方が組み合わさって行われています。とくに、新築住宅やリノベーション物件では、電気工事側が先に配線を行い、その後に空調機器の設置が入るといった“段取りの調整”も必要になります。
このような工事には、次のようなプロセスが伴います。
1. 電気工事業者が分電盤の確認と専用回路の確保
2. 必要に応じて電圧変更やブレーカーの容量変更
3. 空調業者が室内外の機器を設置し、冷媒配管を施工
4. 電気工事業者が接続・通電・絶縁測定を実施
5. 試運転と性能チェックで完了
このように、エアコン工事は決して“単独の簡易作業”ではなく、複数業者の技術と安全管理が密接に関わる複合工事であることが分かります。
エアコン工事の“電気工事部分”を見落とさないことが安全の第一歩
エアコン設置を検討している方は、「配管だけでなく電源工事が必要な可能性がある」という前提で考えることが重要です。
とくに以下のような場合は、電気工事が必須となるケースなので注意が必要です。
【電気工事が必要な具体例】
・ 既存のコンセントが100Vで、200V機器を取り付けたい
・ 専用回路がなく、ブレーカーがすぐ落ちる
・ 屋外設置で防水コンセントが必要
・ 分電盤の回路数が足りない
・ アース端子の施工がない
このような状況で無理に設置を行えば、機器の寿命を縮めるばかりか、重大な事故にもつながりかねません。
したがって、エアコン設置を「空調工事だけの範囲」として認識せず、電気工事を含めたトータルの施工として捉えることが、安心で快適な生活空間をつくる第一歩なのです。
▼ エアコンクリーニング関するご相談や作業の依頼をお考えの方はコチラをチェック <ダスキンほづみ> ▼

👉 エアコンクリーニングなら「ダスキンほづみ」にお任せ!
専門技術による高圧洗浄で内部のカビ・ホコリを徹底除去
ダスキンほづみでは、独自の高圧洗浄技術を駆使して、エアコン内部に付着したカビやホコリをしっかり除去。専用資器材と薬剤を用いて熱交換器まで洗浄し、嫌なニオイの原因を根本から解決します。
分解清掃から抗菌・防カビ処理までの充実プロセス
エアコンの分解・養生からスタートし、ホコリ除去、高圧洗浄、すすぎ、外装の吹き上げ、抗菌・防カビ処理と、一貫したプロセスで清掃を実施。ご家庭では手が届かないエアコン内部までしっかり対応します。
ISO 14001認証取得による環境配慮
ダスキンほづみは、環境マネジメントの国際規格「ISO 14001」を取得しており、環境に優しいサービス提供を行っています。
高い技術力と品質へのこだわり
ダスキンサービスマスターとして、最新技術と丁寧な作業を両立。満足が得られない場合は再実施に応じる品質保証もあり、安心して依頼できます。
清掃+レンタルの総合サービスを展開
エアコンクリーニングに加え、家庭用・業務用の空気清浄機レンタルや、浄水器、マットなど清掃用品のレンタルも提供。豊富なラインナップで、住まい全体の衛生環境をサポートします。
利用メリットとおすすめポイント
| 特長 | メリット |
|---|
| 高圧洗浄技術 | 内部のカビ・ホコリを徹底除去し、エアコン本来の性能を回復 |
| 抗菌・防カビ仕上げ | 洗浄後も清潔が長持ちし、雑菌の繁殖を抑制 |
| ISO 14001対応の安心感 | 環境に配慮したサービスで、安心して依頼できる |
| 総合的な清掃・レンタル対応 | エアコン以外の清掃・快適グッズも一括で相談・依頼可能 |
安心・快適な暮らしを目指す方におすすめ
ダスキンほづみは「エアコンクリーニング」と「清潔・快適な住環境」を両立したプロフェッショナル集団です。高圧洗浄から抗菌処理、さらに環境配慮や多数のサービス展開まで、あらゆるニーズに応える企業としておすすめできます。
🔽詳細は下のリンクからどうぞ🔽
▼ エアコンクリーニング関するご相談や作業の依頼をお考えの方はコチラをチェック <ダスキンほづみ> ▼

エアコンの設置工事ってどんな業者に頼めばいいの?
工事の質は「どの業者に依頼するか」で大きく変わる
エアコンの設置工事は、一見するとどこの業者に頼んでも同じように見えるかもしれません。しかし、実際には業者ごとに得意分野や対応範囲、施工品質に大きな違いがあるのが現実です。
「安いから」「早く来てくれるから」といった理由だけで業者を選んでしまうと、あとで追加料金が発生したり、機器のトラブルが頻発したりすることも少なくありません。とくに、エアコン工事には空調工事と電気工事の両方の知識・技術が必要不可欠であり、施工業者の選定は非常に重要なポイントになります。
以下では、主なエアコン設置業者のタイプ別に、それぞれの特徴や適しているケースを具体的に解説していきます。
家電量販店系の設置業者
メリットと注意点が明確な「価格優先型」
家電量販店でエアコンを購入すると、ほとんどの場合、提携の下請け工事業者が設置に来てくれます。このパターンは「価格が安い」「手続きがシンプル」というメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。
【特徴と傾向】
・ 基本的には「標準工事」の範囲に限定(配管4mまで、壁穴1か所など)
・ 電気工事は別料金、もしくは他業者への再依頼が必要
・ 作業員のスキルにバラつきがあることもあり、現場対応力に限界あり
・ 追加工事(回路増設や電圧変更など)が必要な場合、日を改めて再施工になる可能性あり
このタイプは、一般的な木造住宅でのシンプルなルームエアコン設置に向いていますが、「専用回路が必要」「200Vに切り替えたい」「機器が大型」などの場合には不向きです。
空調専門業者
技術力・柔軟性に優れた「空調設備のプロフェッショナル」
空調専門業者は、住宅からオフィス・店舗・工場に至るまで、あらゆるエアコン機器の取り付けに精通しており、特に次のような場合に力を発揮します。
【特徴と傾向】
・ 冷媒配管、真空引き、ガス補充などの処理が丁寧で信頼性が高い
・ 壁面の強度や室外機の設置環境なども熟知しており、安全性が高い
・ 多くの場合、自社に電気工事士が在籍しており、配線工事も一括対応可能
・ 工事の見積もりが明快で、現場ごとの柔軟な対応が可能
このタイプは、複数台の設置、複雑な配管ルート、高機能機器の導入など、標準を超えた対応が必要な現場に最適です。費用面は量販店より高めになることもありますが、施工の完成度とトラブルの少なさという点では圧倒的に信頼できます。
電気工事業者
電源まわりの整備が必要な現場では“最適解”
空調機器そのものの取り付けは外注となることもありますが、分電盤からの回路引き込み、ブレーカーの増設、200V切替など、電気設備まわりの施工は電気工事業者が本職です。
【特徴と傾向】
・ 国家資格である「電気工事士」が確実に施工を担当
・ 配線図の作成や分電盤の改修など、建物全体の電力設計に基づいた施工が可能
・ 空調機器の性能に応じて、適切な電源容量や遮断装置の選定ができる
・ 空調業者と連携して、機器の取付と電気工事を別日で段階的に行うケースが多い
このタイプは、古い建物で配電設備が不十分な場合や、動力(3相200V)が必要な業務用エアコンの導入時などにおすすめです。特に、電気契約の変更(単3切替など)が必要な場合には、電気工事業者への依頼が必須になります。
ハイブリッド対応型業者(空調+電気をワンストップ対応)
最近増えている“両方できる業者”が理想的
近年では、空調工事と電気工事の両方を一括で対応できる「ハイブリッド型の業者」も増えています。
このタイプの業者は、以下のような特徴があります。
・ 社内に空調技術者と電気工事士が在籍し、一貫施工が可能
・ 設置前の現地調査で、空調機器の配置と電源容量の両面から最適な設計提案ができる
・ ワンストップ対応のため、打ち合わせの手間や工事期間を短縮できる
・ 電気工事部分もすべて施工保証や法的対応が完備されているケースが多い
とくに、省エネ住宅、スマートホーム、店舗の改装など、複雑な条件下での施工では、こうしたハイブリッド業者が高い評価を受けています。
業者選定で見るべきチェックポイント
業者を選ぶ際には、以下のようなポイントを押さえておくと、失敗やトラブルを防ぎやすくなります。
【業者選びのチェックリスト】
・ 施工範囲に「電気工事」も含まれているか明示されているか?
・ 作業スタッフに「電気工事士」の有資格者が含まれているか?
・ 「追加工事費」が発生する場合の条件が明確か?
・ 施工後の不具合に対する保証やアフターサービスがあるか?
・ 見積書の内容が分かりやすく、施工内容が具体的に書かれているか?
これらを事前に確認しておくことで、価格だけでは見えにくい“安心の質”を見極めることができます。

★ 電気工事の依頼について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
電気工事の依頼方法を解説!必要な工事・費用・業者の選び方とは?
空調に関する電気工事を行う際に注意することって何?
施工前の確認不足や誤った判断が「事故」と「トラブル」の原因に
空調設備に関する電気工事は、単に「電源をつなげばよい」というものではありません。むしろ、建物の構造・電力契約・既存の配線状況など、さまざまな要素を踏まえて施工しなければ、思わぬ事故やトラブルの原因となります。
特に以下のようなポイントは、施工前・施工中・施工後のすべての段階で注意が必要です。
「何を」「どのように」気をつければ良いのか──。具体的に整理して解説していきます。
注意点 1:電源容量と配線ルートの事前確認
「既存の分電盤に空きがあるかどうか」が分岐点
空調機器を導入する際は、まず建物の分電盤から機器まで、電源をどう引くかを設計しなければなりません。
このとき、分電盤に空きがなくブレーカーを追加できない場合や、電源容量が不足している場合には、契約アンペアの変更や幹線の引き直しが必要になることもあります。
また、配線ルートにおいても、以下のような事前確認が必要です。
・ ケーブルを通すための隠蔽ルート(壁中、天井裏、床下)の有無
・ 他の回路や通信配線との干渉リスクの確認
・ 高所作業や狭小空間での作業リスク(足場や養生の必要性)
無理な配線や容量オーバーをそのままにすると、火災や感電といった重大事故を引き起こす危険性があります。
注意点 2:専用回路の有無と使用電源の適正確認
複数の機器が同一回路だと“落ちる・止まる・壊れる”
エアコンのように定格消費電力が大きい空調機器は、必ず「専用回路」で運用するのが基本です。
たとえば、電子レンジ・洗濯機・給湯器などと同じ回路でエアコンを稼働させると、以下のようなリスクがあります。
・ ブレーカーが頻繁に落ちる(過電流)
・ 電圧降下によりエアコンが誤作動、停止する
・ 回路やコンセントが過熱し、最悪の場合は発火する
また、100V/200Vの電源種別にも注意が必要です。機器に合わない電源で使用し続けると、機器内部が過熱・焼損し、メーカー保証の対象外になる可能性もあります。
空調設備は必ずそのスペックに応じた電圧・電流・専用回路を確保することが必要不可欠です。
注意点 3:アース(接地)と漏電遮断器の適切な施工
電気の“逃げ場”を確保して感電・漏電を防ぐ
エアコンなどの空調機器は、水気や湿気が近くにある場所に設置されることが多いため、感電リスクが高くなります。
このリスクを防ぐために必要なのが、「接地(アース)工事」と「漏電遮断器の設置」です。
・ アース線が正しく設置されていない場合、漏電時に筐体が帯電して感電する恐れ
・ 漏電遮断器が未設置だと、異常が起きても電気が流れ続ける
特に、鉄筋コンクリート造の建物では地面との絶縁が強くなるため、適正な接地抵抗値(10Ω以下など)を維持するための測定・確認が不可欠です。
保安基準を満たした接地工事をしなければ、法令違反だけでなく命に関わる事態を引き起こすため、軽視してはいけません。
注意点 4:施工業者の「資格」と「責任範囲」の確認
無資格者による電気工事は“法律違反”です
電気工事には、「電気工事士法」により国家資格の取得が義務付けられています。
以下のような作業を行う際には、必ず有資格者が担当しているかどうかを確認しましょう。
・ 分電盤からの専用回路の引き込み
・ ブレーカーの設置や交換
・ アース工事や漏電遮断器の施工
・ 電源の接続や配線処理
また、工事を依頼する際には「登録電気工事業者」であるかどうか、作業内容に対してどこまで保証があるかを事前に確認することも重要です。口頭で「できます」と言われただけでは不十分です。
見積書・契約書・施工報告書などで責任の所在と作業範囲を明記するようにしましょう。
注意点 5:建物の使用条件や周辺環境への配慮
室外機の騒音・振動や景観への影響にも注意
電気工事に直接関わる部分ではありませんが、空調機器の設置場所によっては「電源の引き回し方」に制約が生じることがあります。
たとえば次のようなケースでは、電気配線の取り回しや設置計画に注意が必要です。
・ 室外機の設置場所が道路に面している場合:配線カバーの露出が景観上問題になる
・ バルコニーや狭小地に設置する場合:風通しや排熱が不十分で機器の効率が下がる
・ 振動が建物構造に伝わる場合:建物劣化や騒音クレームの原因に
こうした点を考慮し、「設置のしやすさ」だでなく「周囲への影響」まで見据えた設計と施工計画が求められます。
▼ エアコンクリーニング関するご相談や作業の依頼をお考えの方はコチラをチェック <ダスキンほづみ> ▼


空調工事における電気工事って今後どうなっていくの?
スマート化・省エネ化が進む中で“電気工事の高度化”は避けられない
近年、空調設備は単なる「冷暖房機器」から、エネルギー管理や建物全体の快適性を制御する“インテリジェント設備”へと進化しています。この変化に伴い、空調に関する電気工事もまた、従来のように「配線して電源をつなぐだけ」の作業から脱却し、より高度で多機能な施工が求められる時代へと突入しています。
たとえば、以前はオフィスや工場に限られていた「集中制御システム」や「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」は、今や一般住宅でも採用されるようになりました。
こうした流れの中で、空調工事における電気工事がどのように変化していくのかを、技術面・制度面・市場面の3つの観点から具体的に見ていきます。
技術面の変化:通信・制御・自動化との融合が加速する
空調×電気×IoT=“統合施工”が常識に
IoT技術の普及により、エアコンや換気扇、加湿器などの空調機器は、センサーやネットワークと連携し、自動で稼働・停止・調整を行う時代になっています。
これに伴って、以下のような新しい工事領域が登場しています。
・ 無線LANや有線LANと接続するためのネットワーク配線工事
・ スマート家電連携用の制御盤や分電盤の構築
・ タイマー制御、音声操作、遠隔操作のためのシステム設定
これらの施工には、単に電源を引くだけではなく、制御信号・通信設定・クラウド連携といった、電気通信工事に近い知識が必要になります。
つまり、電気工事士+情報通信技術者の“ハイブリッドスキル”が求められる時代に突入しているのです。
制度面の変化:カーボンニュートラルと電気工事の新たな役割
ZEH・ZEB対応に向けて「省エネ設計」が求められる
国や自治体が主導する「脱炭素化社会の実現」に向け、住宅・建物の省エネ性能の向上が法制化されていく中で、空調設備と電気設備の関係も再定義されつつあります。
たとえば、以下のような制度・施策に対応するためには、従来の電気工事の枠を超えた提案力と設計力が不可欠です。
・ ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):太陽光発電、蓄電池、高効率空調の組合せによるエネルギー収支ゼロ住宅
・ ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル):業務用建物の空調、照明、換気を総合制御することでエネルギー消費を抑制
・ 再エネ特化住宅:電力会社との系統連携を前提とした電力フロー設計とピークカット制御
これらの制度に準拠した設備導入には、電気工事業者が空調の消費電力・負荷特性を理解し、再エネシステムとの整合性を持たせた配線・制御設計を行う必要があります。
今後は「施工できる」だけでなく、「省エネを設計できる」電気工事業者が選ばれる時代になるといえるでしょう。
市場面の変化:多様なニーズと人材不足が交錯する現実
住宅も商業施設も“空調の複雑化”が進行中
かつては「冷える・温まる」ことが求められていた空調設備ですが、現在ではそれに加えて、空気質(CO₂濃度・湿度・PM2.5)や室内騒音、ランニングコストなど、多岐にわたる要素が重要視されています。このため、空調設備の性能を最大限に発揮させるための“最適な電気供給設計”が、設計段階から求められるようになってきました。
一方で、こうした複雑な要件に対応できる電気工事士は全国的に不足しており、技術者の高齢化・若手不足という構造的課題も深刻です。
したがって今後は、
・ 空調と電気を一括提案できる“マルチスキル技術者”の育成
・ ITと連携した「見える化」ツールの活用
・ 遠隔保守やスマートメンテナンスの導入
といった取り組みが、空調電気工事業界の未来を切り拓くカギになるでしょう。
今後の空調工事における電気工事の“進化形”とは?
空調工事における電気工事は、今後以下のような方向に発展・変化していくと考えられます。
【未来の方向性まとめ】
| 進化の方向性 | 内容の説明 |
|---|
| 統合制御の進化 | 空調・照明・換気・セキュリティを一体で制御するための電気設計が主流に |
| エネルギー最適化の要求 | 各空調機器の電力使用量をリアルタイムに監視し、ピークカットや負荷分散を制御 |
| 遠隔操作・自動保守の普及 | ネット経由で空調設備を監視・操作・メンテナンスする電気通信工事の必要性が増大 |
| スマート住宅・施設対応 | 音声認識・センサー・スマホ連携など、多様な入力装置に対応した高機能電源設計が求められる |
こうした変化に対応するためには、空調機器メーカー・電気工事業者・通信設備業者など、多職種の連携と横断的な技術共有が不可欠です。
今後の空調工事では、「空気を冷やす・温める」以上に、“建物全体のインフラ最適化”を担う戦略的な電気工事が求められることになるでしょう。

★ 電気工事の未来などについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
電気工事の未来とは?最新技術と産業構造の変化にどう対応するか
まとめ
空調設備の“快適”を支えるのは、目に見えない電気工事の技術
空調工事と聞くと、まず思い浮かぶのは「エアコンの取り付け」や「配管工事」といった目に見える作業かもしれません。しかし、その快適な空気環境を確実に実現するためには、見えない部分で支えている電気工事の存在が絶対に欠かせません。
電源の確保、専用回路の新設、電圧の適正調整、アースの施工、安全装置の設置など、あらゆる機器の“動作条件”を満たすインフラを整えるのが電気工事の本質的な役割です。
たとえば、どんなに高性能なエアコンでも、適切な電源がなければ性能を発揮できず、誤作動や故障、最悪の場合は火災といった重大な事故に発展する可能性すらあります。
つまり、空調工事と電気工事は決して切り離せない一対の存在であり、「機器」と「インフラ」を同時に考えることが、今後の住環境・業務環境の基準となるでしょう。
“誰に頼むか”で工事の品質と安全性は決まる
今回の記事でも繰り返し述べてきたとおり、空調設備の導入においては、工事の依頼先選びが極めて重要です。
量販店の下請け業者、空調専門業者、電気工事業者、そして最近増えているハイブリッド対応業者──。どの業者にも強みと特徴がありますが、共通して言えるのは、「電気工事が含まれているか」「有資格者が対応するか」を必ず確認すべきということです。
また、見積書の内容が曖昧であったり、施工後の保証内容が不明確であったりする業者には十分な注意が必要です。
施工の安さやスピードだけにとらわれず、“長期的な安全と安心”を見据えた選定が求められる時代です。
スマート化・省エネ化の時代に、電気工事の果たす役割はますます大きくなる
今後、空調工事と電気工事の関係はますます密接に、そして複雑になっていくことは間違いありません。
・ スマートホームの普及により、遠隔制御、音声操作、AIによる自動制御が当たり前に
・ 再生可能エネルギーとの連携で、エネルギー設計そのものが電気工事士の仕事に
・ ZEHやZEBへの対応で、設計段階から電力消費と空調効率のバランスを考慮する必要性が増大
こうした時代の変化に対応するためには、電気工事士としての高度な知識と、空調システムへの深い理解が求められるようになります。
そしてユーザー側もまた、施工の内容とその影響をしっかり理解し、「空調と電気の一体運用」という視点を持つことが重要です。
快適な空間は、電気の設計から始まる
空調設備は、私たちの日常を支える“空気のライフライン”です。そしてそのライフラインを動かすのが、見えない電気工事の技術です。
だからこそ、エアコン1台の設置であっても、適切な電源設計・安全対策・専門的な施工が求められるのです。
快適で安全、そして長く使える空調環境を実現するために──。空調と電気の関係性を正しく理解し、信頼できる業者に相談・依頼することが、最良の第一歩になることでしょう。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼