
電気工事でよくあるトラブルとは?原因と正しい対処法
電気工事は、住宅・オフィス・工場・店舗など、あらゆる場所で快適で安全な生活や業務を支えるために不可欠な作業です。
しかし、現場ではさまざまなトラブルが発生するリスクがあり、原因を正しく理解しておかないと、感電・火災・設備の故障といった重大な被害につながります。
ここでは、電気工事で頻発する代表的なトラブルと原因、そして具体的な対処法を詳しく解説します。
電気工事で発生しやすいトラブルとは?
1. 配線の誤接続
電気工事で最も多いトラブルが、配線の接続間違いです。
例えば、電線の色(黒=電圧線、白=中性線、緑=接地線)を誤って接続すると、ショートや機器の誤作動が起きます。
また、端子台やコンセントへの結線が不十分だと、通電不良や接触不良による発熱を招き、火災の原因になることもあります。
2. ブレーカーが頻繁に落ちる
電気工事後に「ブレーカーがすぐ落ちる」という相談は少なくありません。
これは、回路の容量オーバーや漏電が主な原因です。
エアコンや電子レンジなど消費電力の大きい機器を同じ回路に集中させると、すぐに過電流が流れてブレーカーが作動します。
また、施工時に絶縁不良が起きていると、漏電遮断器が頻繁に作動します。
3. 照明やコンセントが作動しない
「取り付けたばかりの照明が点灯しない」「コンセントに電気が来ていない」といったケースもよくあります。
原因は結線ミスやスイッチ回路の誤配線です。
また、新築やリフォーム時には、図面と実際の施工が食い違うこともあり、施工後に気づいて再工事が必要になることも少なくありません。
4. 感電事故
電気工事において最も危険なトラブルが感電事故です。
家庭用の100Vでも人体に大きなダメージを与え、場合によっては死亡事故につながります。
特にブレーカーを落とさずに作業を始めたり、絶縁処理を怠ったりすることで発生します。
5. 火災事故
配線の劣化や施工ミスにより、ケーブルが過熱して電気火災につながることもあります。
特に古い住宅や店舗では、耐久性の低いケーブルが使用されている場合が多く、電気工事の際に更新されず残されてしまうことで、後に火災のリスクが高まります。
トラブルが起きる主な原因
電気工事のトラブルは、以下の要因から発生することが多いです。
・ 施工ミス:資格を持たない人や経験不足の作業者が工事を行うと、基本的な安全処理を怠るケースがある。
・ 材料不足や不良品:安価なケーブルや端子を使うと、すぐに劣化や断線を引き起こす。
・ 安全確認不足:工事後のテスト(導通試験、絶縁抵抗試験)を行わずに引き渡すと、後にトラブルが発生。
・ 設計段階の不備:回路容量の計算を誤ると、頻繁なブレーカー遮断や発熱を招く。
・ 老朽化した設備を放置:古い配線をそのまま残すことで、施工後も事故の火種が残る。
正しい対処法と再発防止のポイント
電気工事でトラブルが発生した場合、応急処置と根本的な解決が必要です。
1. 安全確保を最優先
・ まずブレーカーを落として通電を遮断します。
・ 感電や火災のリスクを最小限にするため、通電状態での確認作業は絶対に避けることが大切です。
2. トラブルの原因を特定する
・ 施工図面と現場を照合して、誤配線や施工不良がないか確認します。
・ テスターや絶縁抵抗計を使い、配線の異常を測定することも有効です。
3. 部材の交換や修正を徹底する
・ 配線不良や接触不良が見つかった場合は、必ずケーブルや端子を交換しましょう。
・ 応急処置だけでは再発リスクが高まるため、根本的な修正が必要です。
4. 定期点検とメンテナンスを行う
・ 工事後は必ず絶縁抵抗試験や動作確認を行い、記録を残します。
・ 特に業務用施設や工場では、定期的な点検が法律で義務付けられている場合もあるため注意が必要です。
電気工事のトラブルを防ぐために大切なこと
電気工事のトラブルは、ちょっとした施工ミスや準備不足が原因で発生することがほとんどです。
そして一度トラブルが起きると、生活への支障や安全リスクが大きくなるため、正しい対処法を知っておくことが重要です。
・ 配線の誤接続、ブレーカー遮断、感電事故、火災は電気工事でよくあるトラブル。
・ 原因は施工ミス、材料不足、安全確認不足、設計の不備など。
・ 対処法は「安全確保 → 原因特定 → 修正や部材交換 → 再発防止点検」の流れが基本。
電気工事は、必ず有資格の電気工事士に依頼することが最も安全で確実な方法です。
また、依頼する側も最低限の知識を持ち、工事後に動作確認や保証の有無を確認することで、トラブルを大幅に減らせます。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
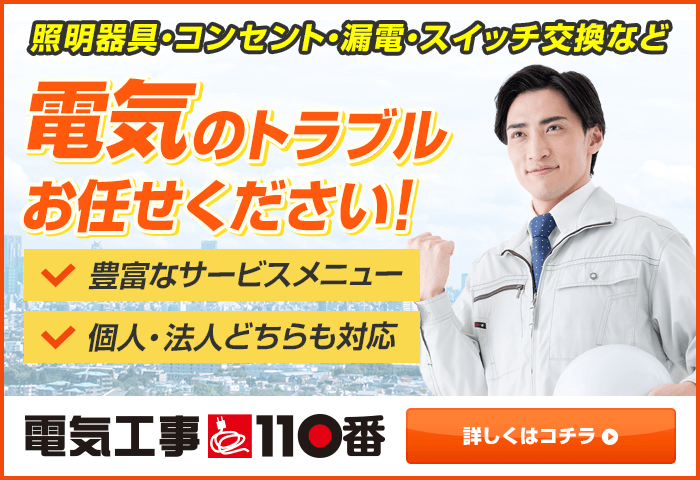
👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
🔽下のリンクから今すぐ『無料相談・見積依頼』が可能です🔽
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
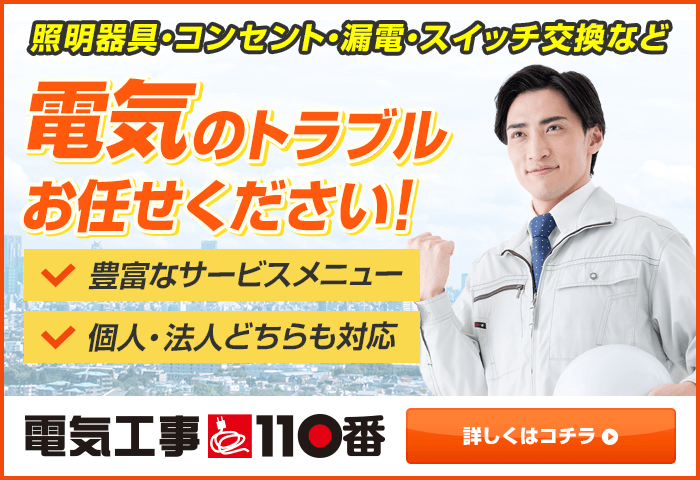
電気工事のトラブルを未然に防ぐ!事前準備とチェックポイント
電気工事の現場で発生するトラブルの多くは、工事開始前の準備不足や確認不足が原因です。
十分な事前準備を行うことで、感電事故・火災・機器不良などのリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、電気工事を行う際に必要な事前準備の具体的な手順と、必ず押さえておきたいチェックポイントを詳しく解説します。
なぜ事前準備が重要なのか?
電気工事は、照明やコンセントの取り付けといった小規模な工事から、高圧受電設備の設置や工場の幹線工事など大規模な施工まで幅広く行われます。
いずれの規模であっても、準備不足が原因で発生するトラブルは非常に多いのが現実です。
例えば、
・ 工具の絶縁不良に気づかず使用 → 感電事故につながる。
・ 図面の確認を怠る → 実際の配線ルートと不一致となり、施工後に不具合発生。
・ 必要部材の不足 → 作業が中断し、無理な代替施工で安全性が低下。
こうしたリスクを排除するためにも、工事前の点検・確認が最重要課題となります。
工事前に必ず行うべき事前準備
1. 図面の最新化と現場確認
・ 最新の施工図面を準備することは、電気工事の基本です。
・ 設計変更や現場の追加要望が反映されていない古い図面を使用すると、配線ルートの誤りや機器の設置ミスが発生します。
・ 必ず現場を下見して図面と比較し、齟齬を洗い出す作業を行いましょう。
2. 工具・測定器の点検
・ 絶縁ドライバー、圧着工具、電工ナイフ、テスター、絶縁抵抗計などを使用前に確認。
・ 絶縁破損や刃こぼれがあれば感電事故の原因になります。
・ 安全性を担保するため、作業開始前に必ずチェックしましょう。
3. 材料・部材の準備
・ ケーブル、コンセント、ブレーカー、ジョイントなど、必要な部材を事前に揃えることが重要です。
・ 特に幹線ケーブルや分電盤部材などは在庫切れで即時調達が難しいため、施工日までに確保しておく必要があります。
4. 安全対策の徹底
・ 作業前に必ずブレーカーを遮断して、無電圧状態を確認します。
・ 作業員全員にヘルメット、絶縁手袋、安全靴を着用させ、安全衛生教育を実施することが推奨されます。
【電気工事前のチェックリスト】
| 項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|
| 図面 | 最新の図面が揃っているか?現場と一致しているか? | 改修工事では図面変更の見落としが多い |
| 工具 | 絶縁工具・テスターに異常はないか? | 絶縁破損は感電事故につながる |
| 材料 | ケーブル・端子・ブレーカーは揃っているか? | 部材不足による施工不良に注意 |
| 安全 | 作業員が保護具を装備しているか? | 装備不足は重大事故を招く |
| 試験 | 絶縁抵抗計での事前確認を行ったか? | 不具合を早期発見する手段になる |
トラブルを未然に防ぐ追加ポイント
1. 負荷計算を必ず行う
・ 家庭用回路でも、過負荷によるブレーカー遮断は頻発します。
・ エアコン、IHクッキングヒーター、電子レンジなど、大電流を必要とする機器は必ず専用回路を設けることが重要です。
2. 施工前の通電確認
・ 工事を開始する前に、施工範囲のブレーカーが正しく遮断されているかを確認します。
・ 通電状態のまま作業を始めると、わずかな接触でも感電する危険性があります。
3. 複数人でのダブルチェック
・ 図面確認や絶縁試験は、一人ではなく複数人でクロスチェックするのが望ましいです。
・ 人為的ミスを最小化でき、事故防止につながります。
事前準備がトラブル防止のカギ
電気工事のトラブルは、工事前のチェック不足が原因で発生するケースが非常に多いです。
そのため、施工前には以下の流れを徹底することが不可欠です。
・ 最新の図面と現場状況の照合。
・ 工具や測定器の点検と整備。
・ 必要部材の準備と数量確認。
・ 作業員の安全装備と教育。
・ 絶縁抵抗試験や無電圧確認の実施。
これらを徹底することで、感電・火災・設備不良といった重大なトラブルを未然に防ぎ、安全で確実な電気工事を実現することができます。

★ 電気工事のトラブルについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
緊急な電気トラブルの対応・対処実例と今後の電気工事の進化とは?











