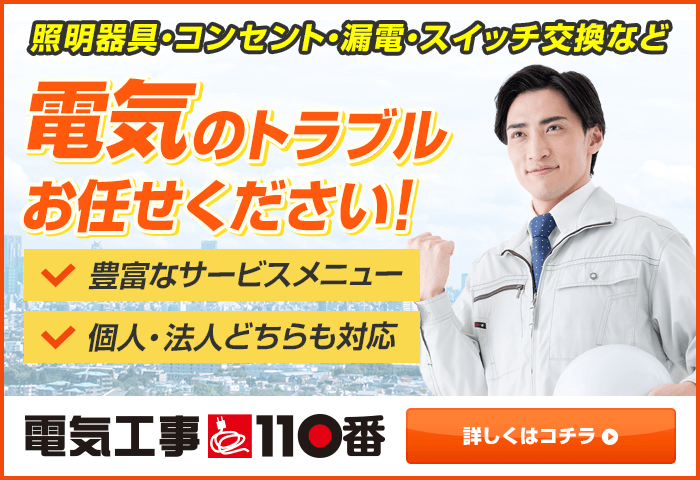店舗の改修工事とは?計画から完成までのステップ
店舗改修工事とは何か?目的と役割を理解する
店舗の改修工事とは、既存の店舗に対して内装・外装・設備・導線などを見直し、より機能的かつ魅力的な空間へと刷新する一連の施工作業を指します。
この工事は単なる修繕にとどまらず、顧客満足度の向上やブランドイメージの再構築、業務効率の改善を目指して行われる戦略的な投資です。
たとえば老朽化が進んだ壁材や床材の更新、照明計画の見直し、スタッフ動線の改善、さらには感染症対策としての換気設備の導入など、時代や業種、立地に合わせた最適化が重要です。
改修工事が必要になる主なケース
以下のような状況において、店舗の改修工事は非常に効果的です。
・ 店舗の老朽化:天井や壁の劣化、設備の不具合が目立ってきた
・ 顧客層の変化:時代のニーズに合わない店舗デザインや機能
・ 売上の伸び悩み:集客力の強化が必要なタイミング
・ 新ブランド展開:既存スペースを活かしてコンセプト変更を行う場合
これらに該当する場合、「今ある空間を最大限に活かす」という視点で改修を計画することが重要です。
店舗改修工事の全体スケジュール
STEP 1:事前計画・目的の明確化
最初のステップは、改修の目的を明確にすることです。
たとえば「集客力の強化」「回遊性の向上」「スタッフの働きやすさ」「ブランド刷新」など、複数の目的を洗い出し、優先順位をつけることが成功の鍵です。
この時点で同時に「改修範囲」と「希望納期」「予算感」もおおよそ決めておきます。
STEP 2:現地調査と法規制の確認
次に、設計会社や施工業者とともに現地調査(現調)を行います。
建物の構造やインフラ状況を確認しながら、建築基準法・消防法・都市計画法などの規制に適合しているかをチェックする必要があります。
特に古い建物の場合、電気容量不足や排水勾配の問題が見つかることもあるため、早期段階での調査が不可欠です。
STEP 3:プランニング・デザイン提案
設計事務所または施工会社から、レイアウトやデザイン、素材の提案が行われます。
この段階では、以下のような検討項目が重要です。
・ 来店者の動線(回遊性)
・ スタッフの動線(作業効率)
・ 什器や家具の配置とデザイン
・ 照明や音響による空間演出
・ 看板、ファサード(外観)、外装の印象
業種やブランドに合ったコンセプト設計を明確にし、視覚的にも機能的にも優れた提案を元に最終案をまとめます。
STEP 4:見積もり取得と契約締結
設計案が固まったら、工事の詳細見積もりを依頼します。
ここでは「内装」「電気工事」「設備工事」「解体・廃材処理」「仮設工事」など、各工事項目ごとの単価・数量・合計金額をチェックします。
金額に納得できた段階で、工期・支払い条件・保証内容を明記した契約を締結します。
STEP 5:着工・工程管理
工事がスタートしたら、工程表に基づいて各工程を順次実施していきます。
施工期間中は、
・ 作業工程の確認
・ 近隣への配慮(騒音・振動)
・ 計画変更時の対応
・ 進捗報告の共有
などが求められます。
特に並行営業を行う場合は、養生・安全対策・営業時間との調整が重要です。
STEP 6:完成・引き渡し・検査
全ての工事が完了したら、現地確認・完了検査・設備の動作確認を行います。
不備があれば手直し対応を行い、最終的に引き渡しとなります。
その後、保証書や取扱説明書の引き渡し、アフターサービス内容の説明が行われます。
店舗改修工事の工程は一体型で進めると効率的
設計・施工を別々の会社に依頼する「分離発注方式」よりも、一貫して設計施工を請け負う「デザインビルド方式(設計施工一体)」が近年主流です。
理由としては以下のようなメリットがあります。
・ コストが一本化されて管理しやすい
・ 工期の短縮が可能
・ 変更や修正の対応がスピーディー
・ 責任の所在が明確
店舗オーナーにとっても、ワンストップで任せられる安心感があり、特に初めての改修工事には適しています。
店舗改修工事は「段取り8割」が成否を左右する
店舗改修工事は、現状把握・目的設定・法令確認・業者選定・工程管理まで、あらゆるプロセスを丁寧に進めることが成功の鍵です。
「工事が始まってから考える」では遅く、着工前の準備段階こそが最も重要な工程ともいえます。
これから店舗のリニューアルや改修を考えている方は、まず信頼できる専門業者に相談し、全体像を把握することから始めてみてください。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
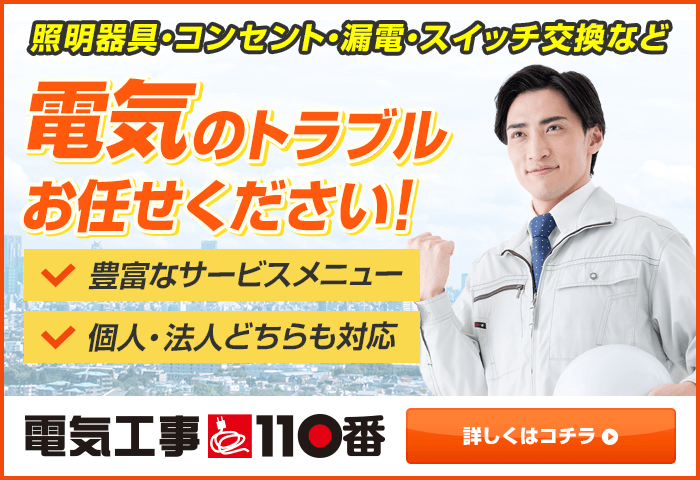
👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
🔽下のリンクから今すぐ『無料相談・見積依頼』が可能です🔽
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
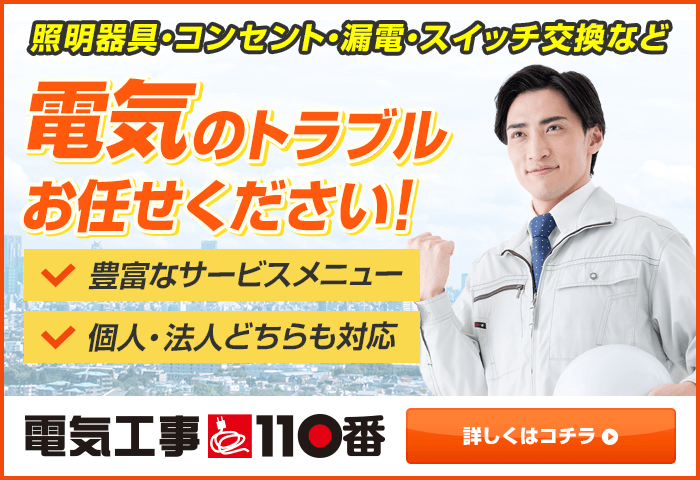
店舗のリニューアル工事を成功させるための基礎知識とは?
リニューアル工事の目的と重要性
店舗のリニューアル工事は、ただ見た目を新しくするだけではありません。
お客様の体験価値を高め、スタッフの働きやすさを向上させ、ひいては売上とブランド価値の向上に直結する重要な投資です。
たとえば「古さを感じさせないモダンな内装」や「回遊性の高いレイアウト」「非接触対応の設備導入」など、リニューアルの切り口は多岐にわたります。
そのため、工事を成功に導くには事前の理解と準備が不可欠です。
以下では、リニューアル工事を計画する際に押さえておきたい基礎知識と具体的な注意点を詳しく解説します。
成功するリニューアルに必要な視点とは?
1. 「目的の明確化」が最優先
まず重要なのは、なぜリニューアルするのか、その目的を明確にすることです。
目的が曖昧なまま工事を進めると、デザインも予算も迷走してしまいます。
【目的別の代表例】
| 目的 | 内容 |
|---|
| 売上の向上 | 購買導線や商品陳列の見直し |
| ブランド刷新 | 店舗コンセプトの一新・世界観の演出 |
| 働きやすさ向上 | 厨房やバックヤードの動線最適化 |
| 節電・省エネ対策 | LED照明や高断熱材への更新 |
| 時代対応 | キャッシュレス対応や換気設備の強化 |
これらの目的を一つに絞るのではなく、優先順位をつけて組み合わせることで、より効果的なリニューアルが可能となります。
2. ターゲット層を的確に設定する
次に考えるべきは、“誰に向けた店舗なのか”を明確にすることです。
ターゲットが明確になれば、内装・照明・BGM・什器デザイン・配色といった細部の演出も一貫性が保たれます。
たとえば、
・ 若い女性をターゲットにしたカフェ → ナチュラルウッド×パステルカラー+SNS映え照明
・ ビジネスパーソン向けのランチ店 → シンプルモダン×高効率レイアウト+回転率重視
のように、顧客に最適化された空間づくりが来店意欲を高め、リピート率の向上につながるのです。
設計・デザイン面での注意点
空間設計は「動線最適化」が命
設計の中でも最も重要なのが「来店者とスタッフの動線の最適化」です。
来店者には、店内を自然に回遊してもらえるような「Z字」や「回遊型」の動線設計を、
スタッフには、レジからバックヤード、厨房までの距離を最短にし、効率的に動ける動線計画が必要です。
【動線設計の具体例】
・ 入口から人気商品の配置を近くする
・ デッドスペースを待合スペースや商品紹介エリアに活用
・ レジ前に手に取りやすい商品棚を設置し、ついで買いを誘発
こうした細やかな設計こそが、売上と顧客体験の質を高める鍵となります。
デザインは「統一感」と「視認性」がカギ
デザインにおいても、業種やブランドの世界観に合わせたトーンを統一することが重要です。
・ 看板、ロゴ、照明、什器の素材感に一貫性を持たせる
・ ロゴカラーを店舗全体のアクセントカラーとして使用する
・ フォントやメニュー表のデザインも全体と連動させる
このようなデザイン設計は、視覚的なブランドの印象を強め、初見のお客様の来店を促す効果もあります。
設備・法令・機能性にも要注意
消防・建築基準法の確認は早めに
店舗の改修には、法的な制限が絡む場面も少なくありません。
・ 避難経路の確保
・ 自動火災報知器や誘導灯の設置
・ 耐火構造や断熱材の使用基準
特に飲食店や不特定多数が利用する施設では、消防署への申請や検査も必要になるケースがあります。
早い段階で業者と相談し、法的なハードルをクリアするための設計に落とし込むことが不可欠です。
最新設備の導入は長期的なコストメリットに
また、リニューアルの機会にあわせて、
・ LED照明
・ 節水型トイレ、洗面台
・ 高効率エアコン、換気扇
・ 非接触対応の自動ドアや決済端末
など、運営コストを下げつつ、ユーザーの利便性を向上させる設備の導入もおすすめです。
初期費用はかかりますが、ランニングコストの削減・衛生面の向上・顧客満足度アップという中長期的メリットが期待できます。
成功事例に学ぶポイントとは?
リニューアル成功店舗の共通点
成功した店舗には共通点があります。
・ 目的とターゲットが明確
・ ブランドイメージを体現するデザイン
・ 動線設計と照明演出が秀逸
・ 予算内で最大の価値を提供する工夫
・ オーナーと業者の連携が密
これらを踏まえ、「見た目」「機能性」「運営性」の3軸でリニューアルを設計することが、失敗しないポイントです。
準備と戦略が、リニューアル成功の鍵を握る
店舗のリニューアル工事は、一度きりの大きなチャンスであり、経営戦略そのものです。
「とりあえずキレイにしたい」という曖昧な動機ではなく、明確な目的と実現したいゴールを持つことが、成功への第一歩です。
その上で、ターゲット設定・空間設計・設備計画・法令遵守を総合的に検討し、信頼できる業者とタッグを組むことが、満足度の高い改修につながります。
次章では、実際に気になる『店舗改修工事の費用相場』について、具体的な事例を交えて解説していきます。

★ 店舗における電気工事について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
店舗の電気工事はなぜ重要?照明・厨房・通信まで支えるインフラ
店舗改修工事の費用の相場とは?
費用相場を把握することの重要性
店舗改修工事を計画するうえで、最も気になるのが「費用はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。
しかし実際には、業種・規模・立地・工事内容によって価格の幅が非常に大きくなるため、一概にいくらとは断言しづらいのが現実です。
それでも、あらかじめ大まかな相場感を知っておくことで、予算計画を立てやすくなり、見積もり内容の妥当性を判断する材料にもなります。
ここでは、店舗改修にかかる主な費用項目と、それぞれの相場について詳しく解説していきます。
業種別・坪単価の目安とは?
まずは、業種ごとに大まかな坪単価の相場を見てみましょう。
坪単価とは、1坪あたりにかかる改修工事の費用のことで、全体の予算感を把握するうえで非常に参考になります。
【店舗改修費用の坪単価(目安)】
| 業種 | 坪単価(税別) | 主な特徴 |
|---|
| 飲食店 | 20万円〜80万円 | 厨房・排気・給排水工事が高額要因 |
| 物販店 | 15万円〜40万円 | 什器・照明・陳列設備中心 |
| 美容室 | 20万円〜70万円 | 給湯設備・個室化ニーズが多い |
| サロン系 | 20万円〜70万円 | 水回り設備・プライバシー確保の間仕切りなど |
| オフィス | 5万円〜20万円 | 間仕切り・OAフロア中心 |
たとえば、20坪の飲食店で中程度の改修を行う場合、400万円〜1600万円程度が一つの目安になります。
具体的な費用項目と内訳
実際の見積もりでは、「設計費」「内装工事費」「設備工事費」など複数の項目に分けて提示されます。
【主な費用項目の内訳】
| 費用項目 | 相場(参考) | 内容例 |
|---|
| 設計・デザイン費 | 工事費の10〜20% | 図面作成、デザイン提案、申請書類作成など |
| 解体工事費 | 坪あたり1万〜3万円 | 既存内装や床材・設備の撤去 |
| 内装工事費 | 坪あたり5万〜20万円 | 壁・天井・床の仕上げ材、塗装、造作など |
| 電気・照明工事 | 20万円〜80万円 | コンセント追加、照明器具取付、分電盤変更など |
| 給排水工事 | 30万円〜150万円 | 厨房・トイレ・手洗い等の新設または改修 |
| 空調・換気設備 | 50万円〜200万円 | エアコン・ダクト工事、換気扇設置など |
| 看板・外装工事 | 20万円〜100万円 | ファサード、看板の設置・交換 |
| 諸経費・管理費 | 工事費の5〜10% | 工事管理、現場養生、清掃、交通費など |
※上記はあくまで目安であり、地域・物価・仕様により異なります。
見積もりに差が出るポイント
複数の業者に見積もりを依頼すると、同じ内容のはずなのに大きな金額差が出ることがあります。
この差の原因としては以下のようなポイントが挙げられます。
【価格差が出やすい要素】
・ 使用する建材のグレード(例:フローリング材や壁材の品質)
・ 什器や設備を既製品かオーダーメイドか
・ 施工手順や下請け業者の数
・ 人件費の地域差(都市部と地方では大きく異なる)
見積もり比較を行う際は、「金額の多寡」だけでなく、「内容の詳細」「使われている材料」「保証やアフターの範囲」も必ずチェックしましょう。
費用を抑えるための考え方
「できるだけコストを抑えたい」と考えるのは当然です。
ただし、必要な部分まで削ってしまうと結果的に損をする可能性もあります。
以下のような視点で「減額可能な部分」「優先すべき投資ポイント」を見極めることが大切です。
コストバランスの考え方
【お金をかけるべき部分】
・ 動線設計、設備工事(スタッフ効率と安全性に直結)
・ 照明、空調(快適さと集客力の向上)
・ 看板、外装(第一印象に大きく影響)
【コストを抑えやすい部分】
・ 壁紙や床材のグレード
・ 家具や什器の再利用やリメイク
・ オープンキッチンやスケルトン天井の採用(あえて見せる設計)
このように、「すべてを高品質にする」のではなく、「効果的に見せる」設計力と取捨選択がコストコントロールの鍵になります。
費用は「設計力」と「目的の明確化」で変わる
店舗改修工事にかかる費用は、一律ではなく条件によって大きく変わります。
だからこそ、設計段階で目的と優先順位を明確にし、適切なプランニングを行うことが最も大切です。
また、見積もりは複数社から取り、工事内容を細かく比較することで、適正価格と信頼できる業者の見極めが可能になります。
次章では、特にニーズの高い『小規模店舗の改修』におけるコストを抑えるための具体策を徹底解説します。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
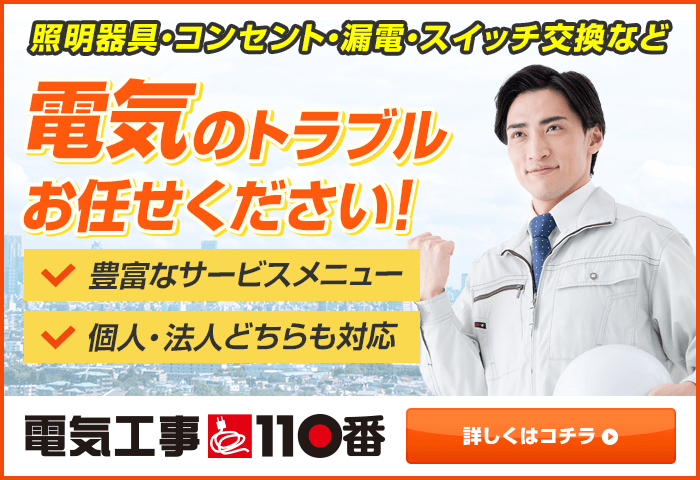

小規模店舗の改修工事、コストを抑えるポイントとは?
小規模だからこそ工夫次第で費用対効果が大きく変わる
小規模店舗の改修工事では、限られた面積と予算内でどこまで効果的な空間づくりができるかが重要です。
特に10坪前後の飲食店・物販店・サロンなどでは、小さな投資でも大きな印象を与えることができるというメリットがあります。
一方で、スペースが限られているため、設備や素材の選び方・施工範囲の設定が費用に直結することも事実です。
そこでここでは、コストを無理なく抑えながら、見た目や機能性を最大限に高めるための具体的なポイントを解説します。
コスト削減の基本戦略は「メリハリ」にあり
すべてを一新するのではなく、必要な部分だけを見極める
全面改修ではなく、ポイントごとに手を加える“部分改修”という発想が小規模店舗には向いています。
【コストをかけるべき部分】
・ ファサード(外観)と看板 → 第一印象を左右する重要ポイント
・ 照明と空調 → 滞在の快適性や店舗の印象を大きく左右
・ 来店者の目に触れる壁面 → 店舗イメージを決定づける面積
【コストを抑えられる部分】
・ バックヤードや倉庫部分 → 機能性重視で見た目の美装は最低限に
・ 什器や家具 → リメイクや中古利用を検討
・ 天井や床材 → 既存活用または安価素材の選定で十分対応可能
このように、「見せ場」と「機能面」で投資のメリハリをつけることが、賢い予算配分の基本です。
小規模ならではの省スペース設計で無駄を削る
面積が狭い分、工夫次第で大きな違いを生む
狭い店舗は、レイアウトや収納の工夫でスペースを有効活用することが必要不可欠です。
また、スペースが少ない分、工事面積が減ることで自然と工事費も下がる傾向にあります。
【省スペース設計の工夫】
・ 壁面収納や吊り棚を活用 → 床面を広く確保し視覚的にも広く感じさせる
・ 移動可能な什器 → 清掃性の向上とレイアウト変更への柔軟性
・ ベンチシートや造作カウンター → 設置コストを抑えつつ座席数を確保
さらに、小さな店舗では照明や内装材の選定で大きな演出効果を狙うことが可能です。
たとえば、間接照明と一部壁面クロスの貼り替えだけでも、一気に空間の印象を変えることができます。
再利用・DIY・ローコスト建材の活用
「使えるものは使う」発想で、無駄なコストを削減
小規模店舗でコストを抑えるためには、新調ではなく再利用の選択肢を積極的に検討することがポイントです。
【再利用・DIYの具体例】
・ 既存のカウンターや棚板をサンディング+塗装で再利用
・ 家具や什器の一部を中古市場やリユース業者から調達
・ 自社でできる範囲(塗装や簡単なクロス貼りなど)をDIYで対応
これにより、什器や家具にかかる数十万円単位の費用を大幅に削減できます。
また、建材も「店舗用」として販売されている高級品にこだわらず、住宅用の建材やノーブランド品を上手に活用することで、低コストで高い質感を実現することが可能です。
営業と並行して工事を進めることで機会損失を防ぐ
工事中も売上を確保する工夫を取り入れる
小規模店舗では、一時閉店が経営に大きく影響を及ぼすため、営業と並行して工事を行うケースが多く見られます。
【コスト削減と営業維持の両立方法】
・ 夜間や定休日のみの施工を依頼
・ 改修エリアを数ブロックに分割し、順番に工事を進める
・ 来店者への丁寧な工事案内と、SNSによる改装中の情報発信
これにより、機会損失を最小限に抑えつつ、改修を進行することが可能になります。
小規模改修は「設計力」と「発想の柔軟さ」が勝負
小規模店舗の改修工事では、限られたスペースと予算を最大限に活かすための“設計力”と“工夫”が何より重要です。
「全部を新しく」ではなく、「必要な部分に集中投資」「再利用やDIYの活用」「営業と工事の並行」など、柔軟で実践的な選択肢を組み合わせることが成功のカギとなります。
少ない投資で最大の効果を得るためには、店舗の特性とオーナーの想いを的確に理解してくれる業者との連携も欠かせません。
次章では、『売上を上げるための内装・照明のリニューアル術』について、さらに掘り下げてご紹介してまいります。

▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
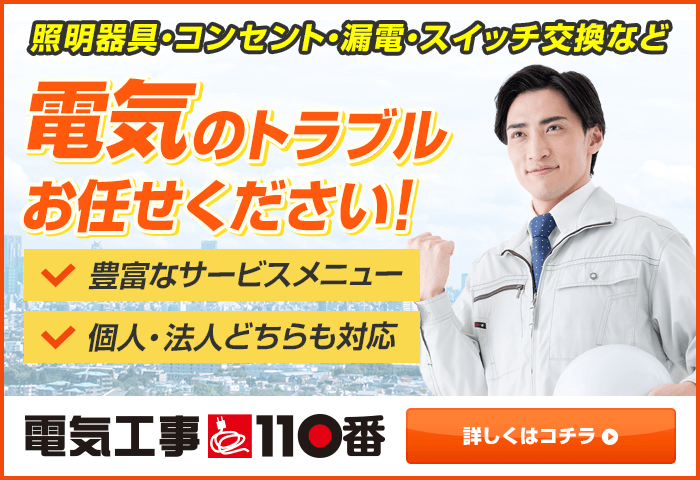
内装から照明まで!売り上げを上げる店舗のリニューアル術とは?
店舗リニューアルの本質は「体験価値の最大化」
店舗のリニューアルは、単に古くなった内装を一新するだけではありません。
重要なのは、顧客の満足度を高め、購買意欲を刺激する空間を創ることです。
売上向上を実現するには、「来店者の動線設計」「空間の快適性」「商品との相性」「滞在時間の延長」といった複数の要素を内装や照明の工夫で最適化することが不可欠です。
ここでは、店舗の印象を左右する内装と照明の具体的なリニューアル術を業種別に紹介しながら、売上アップへとつなげる戦略を詳しく解説します。
内装リニューアルの基本は「視線」と「導線」
お客様の“動き”と“目線”をデザインする
内装設計では、顧客が店内でどう動き、どこを見るかを設計段階で想定しておく必要があります。
導線がスムーズで、視認性が高く、過ごしやすい空間は、無意識のうちに購買を後押しする効果があります。
【売上を意識した内装設計の基本】
・ 入口から店舗奥までの「視線の抜け」を意識:先が見通せることで安心感と興味を引き出す
・ 回遊型のレイアウトを構築:U字またはZ字型で店内を歩かせることで自然な購買導線を確保
・ アイキャッチポイントの設置:新商品棚やプロモーションエリアなど視線を集める工夫
さらに、業態ごとの特徴に応じて内装の“見せ方”を調整することも重要です。
| 業態 | 内装の工夫ポイント |
|---|
| 飲食店 | カウンターとテーブル席の視覚的仕切り+温かみのある色使い |
| 物販店 | 商品棚の高さと間隔で開放感を演出+導線確保 |
| サロン系 | ゆったりした椅子配置と目線を遮るパーテーション |
売上に直結する照明計画の工夫とは?
照明は空間演出と購買心理に直結する武器
照明は「明るくすればいい」という単純なものではありません。
照明の色温度・配置・照度・演出方法によって、店舗の印象や売上は大きく変化します。
たとえば、食品を扱う店舗では温かみのある電球色が食欲を刺激し、アパレルでは自然光に近い昼白色が色味の確認に適しています。
【照明による演出テクニック】
・ ベース照明(全体照明):店内全体の明るさを確保する
・ スポット照明(商品照明):注目させたい商品に光を集中
・ 間接照明(演出照明):壁面や天井を照らして高級感や奥行き感を演出
・ 調光機能の活用:時間帯や天気に応じて雰囲気を柔軟に調整
また、LED照明の導入により電気代を抑えつつ、演色性(色の見え方)が高い製品を選べば、商品や料理がより魅力的に見えるようになります。
売れる店舗は「五感」を刺激している
視覚・聴覚・触覚まで意識したリニューアル
売上を上げる店舗は、ただ“キレイ”なだけでなく、顧客の五感に訴えかける演出が施されています。
【五感を意識した演出例】
・ 視覚:色彩、照明、ディスプレイレイアウト
・ 聴覚:BGMのジャンルや音量、リズムの調整
・ 触覚:椅子の座り心地、床の素材感、壁面の質感
・ 嗅覚:香りの演出(カフェやアパレルで特に有効)
・ 味覚:飲食系の場合、試食スペースの設置で体験を促進
これらを総合的に組み合わせることで、記憶に残る体験としての店舗空間が完成し、再来店の動機にもつながるのです。
スマート導線・非接触対応の導入もリニューアル成功の鍵
感染症以降のニーズにも対応するアップデートを
近年のリニューアルでは、快適性だけでなく安全性や非接触性のニーズも高まっています。
・ 自動ドアやセンサー式照明の導入
・ キャッシュレス決済端末の増設
・ パーテーションや吸音材による安心感の演出
このような配慮は、ユーザーの信頼感と居心地の良さに直結し、結果として売上や店舗評価の向上に貢献します。
空間演出こそが売上を伸ばす最強の施策
内装・照明は、店舗における“営業マン”のような存在です。
第一印象で来店を促し、心地よい滞在を通じて購買意欲を育て、再訪を自然と引き出します。
売上を伸ばしたいと考えるなら、まずは「顧客が何を感じ、どう動き、どこで購買意欲を高めるか」を徹底的に考え抜いた空間設計が必要です。
そして、それを形にしてくれる信頼できるパートナーとの協働こそが、成功への近道です。
次章では、老朽化した店舗をどのように再活用するかという観点から、『空テナントのリニューアル活用事例』について具体的に解説していきます。
★ リフォーム時の電気設備について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
電気設備の見直しで暮らしが変わる!リフォーム時にやるべき工事とは
老朽化した店舗を一新!空テナントの再活用事例
空き店舗が“資産”に生まれ変わる時代へ
近年、商店街や駅前などに増え続けている「空きテナント」は、地域課題として注目される一方で、活用次第では大きなビジネスチャンスにもなります。
特に築年数の古い建物は、老朽化しているから使えないと思われがちですが、実はリノベーションによって価値を大きく向上させることが可能です。
構造がしっかりしていれば、設備や内装を一新するだけで、雰囲気や用途がガラリと変わり、まったく新しいコンセプトの店舗として再生できます。
ここでは、老朽化した空きテナントを有効に活用した実際の事例や再生のポイントを紹介します。
事例 1:築40年の元喫茶店をカフェ兼コワーキングスペースへ再生
Before:木造2階建ての老舗喫茶店、長年空室状態
After:1階はカフェスペース、2階はシェアオフィスに改修
【改修のポイント】
・ 元のカウンターと厨房を再利用してコスト削減
・ 無垢材の床とレトロな照明で“懐かしさ”を演出
・ 2階には個室ブースを設け、静かなワークスペースとして活用
この事例では、「昔ながらの喫茶店の雰囲気」を逆に活かし、若者層に支持される“ノスタルジック”な空間として再生しました。
内装材や家具も可能な限り既存のものを再利用し、工事費を350万円以内に抑えることに成功しています。
事例 2:空き雑貨店をDIYと簡易改修でアパレルショップに転用
Before:駅前商店街の約8坪の小型店舗
After:古着とハンドメイド雑貨を扱うコンセプトショップに
【改修のポイント】
・ 壁は既存のベニヤにペンキ塗装+間接照明で演出
・ 床材はクッションフロアを上貼りしてイメージ刷新
・ 什器やハンガーラックはDIYで自作し、内装コストを大幅に削減
このように、手作り感とオーナーの世界観を全面に押し出した空間づくりが話題となり、SNSでも拡散されました。
費用はわずか100万円以下に抑えられており、スモールスタートを希望する事業者にとって非常に参考になるモデルケースです。
事例 3:空きスナックをナイトヨガスタジオにリノベーション
Before:昭和感漂うカラオケ付きスナック店舗(約12坪)
After:夜間利用に特化した“照明演出型”ヨガスタジオへ
【改修のポイント】
・ 壁面ミラーや間接照明を設置し、暗さを逆に演出へ転用
・ カラオケブースを更衣室として改装
・ 防音性能が高かったため、そのままスタジオ用途に適応
本来、スナック店舗は飲食以外には使いづらいイメージがありますが、音響・防音・照明といった設備を活かし、まったく別の用途へ転換した好例です。
設備の再利用と照明演出の工夫により、工期も1カ月未満、予算は約200万円に抑制されています。
空き店舗を再生するための5つのポイント
空きテナントを有効に活用するには、以下のような視点での設計・改修が効果的です。
【空きテナント再生のチェックリスト】
| ポイント | 解説 |
|---|
| 1. 建物構造の健全性 | 屋根・壁・床・配管の状態を事前に確認し補強要否を判断 |
| 2. 設備の流用可否 | 厨房・エアコン・トイレなどを流用できればコスト削減に |
| 3. デザインの方向性 | 古さを“味”に変えるレトロ路線 or 全面刷新の選択 |
| 4. 用途変更の可能性 | 飲食→物販など業種転換に伴う法的要件の確認 |
| 5. 近隣との調和性 | 周囲の街並みや客層に馴染む業態・内装が好ましい |
これらを踏まえたリノベーション計画を立てることで、資産価値の向上だけでなく、地域への貢献や話題性にもつながります。
空き店舗の再生は、低コスト高効果のビジネス戦略
老朽化した空き店舗も、視点と工夫を変えれば、再び“活きた空間”として大きな価値を発揮できます。
とくに近年は「低コストで始めたい」「個性ある店舗を作りたい」というニーズが高まっており、あえて空きテナントを選び、再生させるという選択肢が注目されています。
そのためにも、既存設備をどう活かすか、どこに費用をかけるかの判断が非常に重要です。
次章では、営業を続けながら改修工事を行う際の段取りと注意点について詳しく解説します。
業務を止めずに売上を維持したまま改修を成功させるためのヒントをお伝えします。

▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
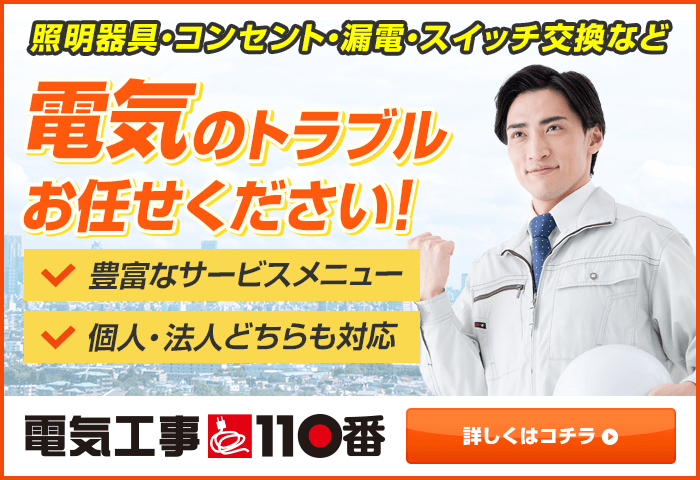

営業しながら店舗の改修工事はできるの?段取りと注意点
売上を止めないための“並行改修”という選択肢
店舗の改修工事は通常、一時的に営業を休止して行うものというイメージがあります。
しかし、実際には「閉店すると売上がゼロになってしまう」「常連客に迷惑をかけたくない」などの理由から、営業を続けながら工事を進める“並行改修”のニーズが非常に高まっています。
もちろん、営業中に工事を進めるにはリスクや制約もありますが、適切な段取りと注意点を押さえておけば、業務と改修の両立は十分可能です。
ここでは、営業と改修を両立させるための具体的な工程管理・配慮点・事例を詳しくご紹介します。
営業しながらの改修工事は可能か?<結論:条件次第で可能>
条件がそろえば「営業しながらの改修工事」は現実的に実行可能
業種や店舗構造、工事内容によっては、営業中でも工事を進められるケースが多く存在します。
たとえば以下のようなパターンでは、改修を段階的に分けて行うことで業務への影響を最小限に抑えることができます。
【営業と改修を両立させやすい条件】
・ 店舗面積にある程度の余裕がある
・ 営業エリアと改修エリアを明確に分けられる
・ 夜間や定休日に施工可能な業者が対応してくれる
・ 騒音や振動が少ない内装工事が中心である
また、飲食店や物販店などでは、厨房・バックヤード・トイレなどの工事を営業時間外に進めることで、営業中の支障を回避できます。
段取りの基本は「工程の分割」と「時間帯の最適化」
工事を分けて、営業しながら順番に進める
営業と並行する改修では、工事を一括ではなく分割で実施するスケジューリングが基本です。
【例:20坪の店舗を営業しながら改修する工程】
| 工事工程 | 時間帯 | 対応方法 |
|---|
| バックヤード改修 | 営業外の夜間 | 工事区画を仕切り、音に配慮 |
| 客席半分改修 | 平日昼間 | 仮設壁で区切り、別席で営業継続 |
| トイレ設備更新 | 定休日 | 事前に代替トイレを設置 |
| ファサード更新 | 夜間・早朝 | 周囲へ養生シート+音出し制限対応 |
このように、「どこを・いつ・どの順番で改修するか」を事前に細かく工程表に落とし込み、業者・スタッフと共有することが最重要です。
騒音・臭気・安全対策への配慮は不可欠
お客様の不快感を避ける工夫を徹底する
営業中の工事で最も気をつけるべきなのが、騒音・振動・塗料の臭気・作業員の出入りなどによるお客様への心理的ストレスです。
【お客様・近隣への配慮チェックリスト】
・ 工事音が出る作業は営業時間外に設定
・ 作業エリアに養生シートやパーテーションを設置
・ 塗料や接着剤は低臭タイプや速乾性のものを使用
・ 工事の案内掲示やポスターを見やすく掲示
・ 作業員の出入り動線を来店客と分離
また、スタッフからも「本日は〇〇エリアの改装工事を行っております。ご迷惑をおかけいたします」という丁寧な声掛けや案内を行うことで、不安や不満を未然に防ぐことが可能です。
並行営業の成功事例に学ぶ
事例:改修中も常連客が増加した飲食店のケース
ある焼き鳥店では、厨房機器の一新・トイレの洋式化・客席の一部改装を、すべて営業しながら段階的に実施しました。
【成功のポイント】
・ 毎週月曜日のみ工事日とし、他日は通常営業
・ 仮設トイレの設置と清掃を徹底
・ 店頭に改装進捗ボードを設置し、工事を“イベント化”
結果として「お店がどんどん綺麗になる過程を見られるのが楽しい」と常連客からの来店頻度がむしろ上昇しました。
このように、営業と改修をポジティブな話題に変える工夫が成功の秘訣となります。
営業と改修の両立は「段取り力」と「顧客配慮」が鍵
営業しながらの改修工事は、簡単ではないものの、適切な計画と業者の協力があれば十分実行可能です。
特に大切なのは、以下の3点です。
・ 明確な工程分割とスケジューリング
・ お客様へのストレス配慮と丁寧な情報提供
・ 現場との連携と日々の進捗確認
事前準備をしっかり行い、オーナー・スタッフ・業者が一体となって進めることで、売上を落とさずに店舗を進化させることができます。
次章では、改修工事の成否を左右する『業者選び』に焦点をあて、信頼できる改修業者の見極め方について詳しく解説いたします。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼
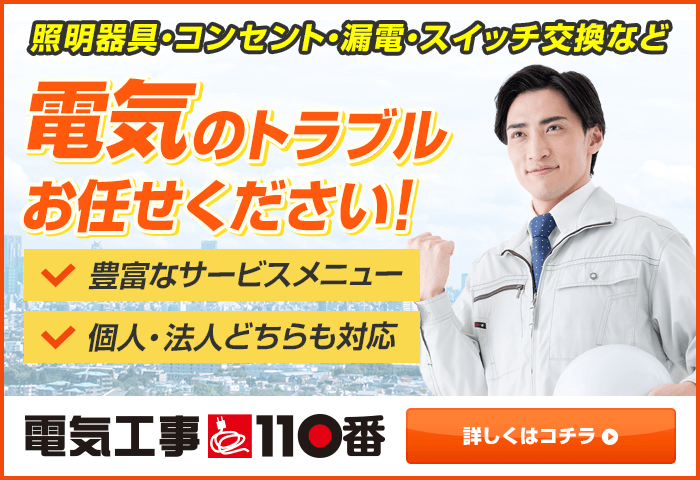
業者選びに失敗しないために!信頼できる改修工事業者の見極め方
業者選びは“工事の成功・失敗”を分ける最重要ポイント
店舗の改修工事を成功させるには、設計やデザインももちろん重要ですが、「誰に依頼するか」が最も大きなカギを握ります。
なぜなら、同じ設計図・同じ予算であっても、業者の施工品質や現場管理の能力によって、完成度には大きな差が出るからです。
「金額が安かったから…」という理由だけで選んでしまい、工事の質が悪かった・工期が遅れた・アフターフォローがないなどのトラブルに発展するケースは少なくありません。
ここでは、信頼できる業者を選ぶための具体的なチェックポイントと、失敗しないための注意点を詳しく解説します。
業者選定でありがちな失敗例とは?
よくある“失敗パターン”を知っておくことが予防につながる
【業者選びの失敗例】
・ 「知り合いの紹介だから」と見積もりを取らずに依頼 → 費用や品質の比較ができず、相場より高額に
・ 工事中に頻繁に追加費用を請求される → 事前の見積もりが不明確だったため
・ デザインと施工を別会社に依頼 → 責任の所在が不明瞭になりトラブルに
・ 完成後の不具合に対応してくれない → アフターフォロー体制がない業者だった
これらのトラブルは、事前の情報収集と確認さえ行っていれば防げる内容ばかりです。
大切なのは、金額ではなく「信頼性」と「実績」で選ぶことです。
信頼できる業者を見極める7つのチェックポイント
1. 施工実績が豊富か?
過去にどのような店舗を手がけたかを確認しましょう。
業種や業態が自店舗に近い施工実績があれば、設計の提案力や現場対応力が高い可能性が高いです。
【確認すべき資料】
・ 施工事例集
・ 施工写真(ビフォーアフター)
・ 顧客からの評価やレビュー
2. 見積書の内訳が詳細か?
信頼できる業者は、見積書の項目を「どこにいくらかかるか」明確に記載します。
曖昧な項目(例:「一式」「応相談」など)が多い業者は避けましょう。
3. 質問や変更への対応が丁寧か?
対応スピードや言葉遣い、メールの文章力なども重要です。
誠実に対応してくれる業者は、現場でも丁寧な仕事をする傾向にあります。
4. 設計・デザインから施工まで一貫して対応できるか?
デザイン会社と施工会社が分離していると、責任の押し付け合いになるリスクがあります。
設計から施工まで一貫対応の「ワンストップ型業者」が理想的です。
5. 工期や工程の説明が具体的か?
スケジュール表(工程表)を提示してくれる業者は信頼性が高いです。
工程の段取りや予備日(予期せぬ工期延長)についても説明があるかを確認しましょう。
6. 契約内容や保証が明確か?
契約書に記載されるべき内容は以下のとおりです。
・ 工事内容と範囲
・ 総工費と支払い条件
・ 着工日、完了予定日
・ 保証期間と対象内容
口約束ではなく、必ず文書で残すことがトラブル防止に繋がります。
7. アフターサポートの有無
工事後の不具合(例:建具の不具合、配線のトラブルなど)に対して、どのような対応をしてくれるのかを事前に確認しましょう。
定期点検や1年保証、緊急対応の有無など、サービス内容も業者選びの基準となります。
比較検討は必須!相見積もりをとることの重要性
「3社以上に依頼」して比較するのが基本
改修工事を依頼する際は、必ず複数社に見積もり依頼(相見積もり)を取ることが重要です。
【比較すべきポイント】
| 項目 | 比較ポイント |
|---|
| 費用 | 坪単価・項目別内訳・追加費用の有無 |
| 提案内容 | レイアウト案・素材の選定・動線計画など |
| 工期 | 着工〜引き渡しまでの日数 |
| 対応 | 説明のわかりやすさ・レスポンスの速さ |
単純に「安い業者が良い」とは限らないため、内容のバランスを見て総合的に判断することが成功への近道です。
業者選びは“価格より信頼性”で決めるべき
店舗改修工事における業者選びは、予算内で理想の店舗を実現するための最重要フェーズです。
そのためには、「安いから」「知り合いだから」ではなく、実績・説明力・対応力・アフターサービスの4要素を基準に慎重に選定する必要があります。
信頼できる業者と出会うことができれば、工事はスムーズに進み、結果として長期的なコスト削減にもつながります。
次章では、ここまでの内容をふまえ、『店舗改修工事を成功させるための総括と実践アドバイス』としてまとめをご紹介します。

★ リフォーム時の配線工事について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください
リフォームで見直すべき配線工事とは?見えないインフラの最適化を
まとめ
店舗改修工事は“経営戦略の一環”として捉えるべき
ここまで、店舗の改修工事に関する一連の内容を、計画から業者選び、コスト削減術、具体事例、並行営業の工夫まで網羅的に解説してまいりました。
改めてお伝えしたいのは、店舗改修工事は単なる「修理」や「模様替え」ではなく、売上・集客力・スタッフの働きやすさを高めるための“経営戦略”のひとつであるということです。
中途半端な改修では、むしろコストばかりがかかり、成果に結びつかないという事態にもなりかねません。
だからこそ、「目的の明確化」「動線・照明・導線設計」「信頼できる業者選定」「段取りの徹底」など、事前の準備を丁寧に行うことが、何よりも重要です。
成功する店舗リニューアルの共通点
ここまでの内容を踏まえ、店舗改修工事を成功に導くための“共通項”を以下にまとめます。
【成功する改修工事の6つの要素】
1. 改修の目的と優先順位が明確である
2. ターゲット層に合わせた空間設計がなされている
3. 費用対効果を意識し、必要な部分に投資されている
4. 営業を止めずに工事を進める段取りができている
5. デザインと機能性のバランスが取れている
6. 実績豊富で信頼できる業者に施工を依頼している
これらが揃えば、顧客満足度・従業員満足度・売上・評判といった“店舗の総合的価値”が着実に向上していきます。
今後のアクションプラン
もし、これから店舗の改修やリニューアルを検討しているのであれば、まずは以下のステップから始めてみてください。
【改修工事を成功に導くアクションフロー】
| ステップ | 内容 |
|---|
| 1. 課題整理 | 現状の問題点や改善したいポイントを洗い出す |
| 2. 目的設定 | 改修の目的(売上向上、ブランド刷新など)を明確に |
| 3. 予算計画 | 全体予算と上限額、支払方法を想定する |
| 4. 業者選定 | 相見積もりを取り、信頼できるパートナーを探す |
| 5. 工事スケジュール調整 | 営業との並行計画・段取りを確立 |
| 6. 着工・進捗管理 | 現場の進行を確認しながら、必要に応じて調整 |
| 7. 完成・アフター対応 | 不具合の確認・修正、営業再開の広報を実施 |
この流れを踏まえておけば、大きなトラブルなく、期待通りの仕上がりを実現しやすくなります。
最後に:リニューアルは“変化の時代”を生き抜くための手段
今の時代、顧客ニーズは急速に変化しています。
スマートフォンの普及、キャッシュレス対応、SNS集客、感染症対策など、店舗に求められる役割と機能は年々多様化・高度化しています。
だからこそ、定期的な店舗改修によって「今の時代に合わせた空間」へと進化し続けることが、ビジネスを長く続けるための鍵となるのです。
改修には費用も時間もかかります。
しかし、それ以上のリターンを得られる可能性があるからこそ、慎重かつ前向きに検討する価値がある投資です。
あなたの店舗が、より魅力的に、より機能的に、そしてより多くの人々に愛される場所となることを、心より願っています。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック <電気工事110番>▼