電気工事
2024.07.18
電気工事の増設工事とは?コンセントやLAN配線など徹底解説

電気工事の増設工事とは?対応できる設備とDIY不可なケース
電気工事の増設工事とは、既存の建物や設備に新しい電気配線・機器を追加して利便性や安全性を向上させる工事のことです。
一般住宅、マンション、店舗、オフィス、工場など、あらゆる建物で行われており、生活や業務の変化に合わせて必要な電気設備を後から追加できるのが大きな特徴です。
例えば、「テレワークでパソコンやプリンターを置くデスク周辺にコンセントが足りない」、「新たにIHクッキングヒーターやエアコンを導入するが専用回路がない」、「オフィスのレイアウト変更に伴いLAN配線を増やしたい」といったケースでは、増設工事が効果的です。
なぜ増設工事が必要になるのか?
現代の暮らしやビジネス環境は、電化製品・ネットワーク機器の使用量が増え続けているのが現状です。
昔の住宅やオフィスは、当時の家電使用量を前提に設計されており、コンセントの数や配線容量が現代のニーズに合わないことが多くあります。
特に以下のような状況では、増設工事が必要になる可能性が高いです。
・ 新しい家電やOA機器の導入
・ テレワークやオンライン授業の開始
・ 店舗やオフィスのレイアウト変更
・ LAN配線の増設や通信環境の改善
・ 電気容量不足によるブレーカー落ち頻発
安定した電力供給と安全性を確保するためには、延長コードやタコ足配線ではなく、適切な増設工事を行うことが不可欠です。
増設工事で対応できる主な設備
増設工事では、単にコンセントを増やすだけではなく、用途や場所に応じた幅広い電気設備の追加・改善が可能です。
以下に代表的なものを挙げます。
【電気工事の増設工事で対応できる設備と施工ポイント】
| 設備 | 主な用途 | 施工時の注意点 |
|---|---|---|
| コンセント | 家電・PC・充電器などの電源確保 | 分電盤容量の確認と配線ルートの確保 |
| 照明器具 | 作業効率や快適性の向上 | 明るさ・色温度・スイッチ位置の最適化 |
| LAN配線 | 安定した通信速度の確保 | 壁内配線やモール施工の美観配慮 |
| ブレーカー | 電気容量不足の解消 | 契約容量変更や安全性能の向上 |
| 専用回路 | エアコン・IH・EV充電など大電力機器用 | 他回路への負荷影響を防止 |
| 防犯カメラ・インターホン | 防犯・セキュリティ強化 | 電源確保と配線経路の安全性 |
| アース工事 | 感電防止やノイズ低減 | 家電の保護と安全性確保 |
このように、増設工事は生活の快適さや業務の効率化、そして安全性向上に直結する重要な施工です。
DIYでは対応できないケースとその理由
電気工事の増設は、第二種電気工事士以上の資格が必要な作業が多く、無資格で行うことは電気工事士法により禁止されています。
無資格での施工は、感電事故・火災・漏電などの重大なトラブルを引き起こすリスクが高く、さらに保険の適用外になる可能性もあります。
特に以下のような工事はDIY不可です。
・ 分電盤からの新規回路増設
・ ブレーカーの増設や交換
・ 200V機器用の専用配線
・ 壁内や天井裏を通す隠蔽配線工事
・ 高所や屋外での防水コンセント増設
これらの作業は、電気の知識・工具・安全管理技術が必須です。
素人判断で配線を行うと、接続不良や絶縁不良により発火事故や機器破損につながるため、必ず有資格の電気工事士へ依頼しましょう。
安全性と長期的な安心を確保するために
電気工事の増設は、一見シンプルな作業に見えても、配線容量のバランスやブレーカー負荷の計算など、専門的な知識が不可欠です。
また、見た目だけきれいに施工しても、内部の配線処理が不適切だと数年後にトラブルが発生する可能性があります。
有資格の電気工事士であれば、施工後に絶縁抵抗測定や電圧確認を行い、長期間安心して使える環境を提供できます。
さらに、将来の増設や機器入れ替えにも対応しやすい設計をしてくれるため、長期的なコスト削減にもつながるのです。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
👇 下のリンクから『無料相談・見積依頼』が可能です / 今すぐチェックを!!
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
コンセントを増設する電気工事の流れと工事前のチェックリスト
コンセントの増設は、日常生活や業務環境を快適にするために非常に有効な電気工事のひとつです。
しかし、安全性や法令遵守の観点から、正しい流れと事前準備が欠かせません。
ここでは、実際の工事のステップと、施工前に必ず確認すべきポイントを詳しく解説します。
工事の基本的な流れ
1. 現地調査と要望ヒアリング
まず電気工事士が現地を訪問し、配線経路や分電盤の容量を確認します。
この際、増設するコンセントの設置場所や使用予定の電化製品の種類・消費電力もヒアリングします。
例えば、パソコンやスマート家電程度なら一般回路で対応可能ですが、IHクッキングヒーターやエアコンなどは専用回路が必要です。
2. 配線ルートと施工方法の決定
調査結果をもとに、壁内配線・モール施工・露出配線など、美観と安全性を両立したルートを選びます。
壁や天井の構造によっては、工事方法や所要時間が大きく変わります。
また、同時に将来的な増設や家具配置の変更も考慮し、最適な位置を提案してもらうことが重要です。
3. 工事前の安全確認と電源遮断
作業前に分電盤の該当ブレーカーを必ずオフにし、電圧測定で通電していないことを確認します。
この工程を怠ると感電事故や機器損傷の危険があるため、電気工事士法でも厳格に求められています。
4. コンセント増設作業
選定したルートに沿って配線を敷設し、コンセントボックスを取り付けます。
壁内施工の場合は、必要に応じて壁に穴を開け、既存配線と接続します。
この際、結線の確実性と絶縁処理が最重要ポイントです。
5. 動作確認と仕上げ
増設したコンセントに電圧をかけ、正常な電圧(100Vまたは200V)が供給されているかを測定します。
その後、通電状態で実際に機器を接続し、過熱や異音がないか確認します。
問題がなければカバーを取り付け、施工完了です。
工事前に必ず確認すべきチェックリスト
以下は、工事依頼前に確認しておくべき項目です。
これらを事前に把握することで、スムーズかつ安全な施工が可能になります。
【工事前チェックリスト】
・ 設置場所の用途
使用する家電や機器の消費電力を把握する
例:PC・プリンター=低消費電力、IH・エアコン=高消費電力
・ 既存配線の容量
分電盤やブレーカーの容量を確認し、容量不足によるブレーカー落ちを防ぐ
・ 配線ルートの障害物
壁や床下に配管・下地・断熱材などの障害物がないかをチェック
・ 美観と安全性のバランス
露出配線を避けたい場合は、壁内配線やモール施工を検討
・ 将来のレイアウト変更
家具や機器の配置替えを想定し、利便性の高い位置に設置
失敗を防ぐためのポイント
1. 延長コードやタコ足配線で代用しない
見た目が手軽でも、発熱や火災の原因になるため危険です。
2. 資格を持つ電気工事士へ依頼する
特に分電盤からの回路増設や200V対応は、必ず有資格者が施工すべきです。
3. 予算だけで業者を選ばない
安価でも施工品質が低いと、数年後に再工事やトラブルのリスクがあります。
この工程とチェックリストを押さえておけば、コンセント増設工事は安全かつ長期的に安心できる設備投資になります。
次は、この増設に深く関わるブレーカー増設工事の必要性と電気容量不足の解消方法について詳しく解説します。

★ コンセントについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
安全な電気工事のために知っておきたいコンセントの基礎知識
ブレーカー増設工事の必要性と電気容量不足を解消する方法
現代の住宅やオフィスでは、家電製品やOA機器の増加に伴い、電気容量不足が深刻な問題になるケースが増えています。
ブレーカーが頻繁に落ちる、同時に複数の機器を使用できないといった不便さは、業務効率の低下や生活のストレスにつながります。
こうした状況を根本的に解消するために有効なのが、ブレーカー増設工事です。
ブレーカー増設が必要になる主なケース
1. 家電製品の増加による容量不足
昔の住宅は、現在ほど家電が普及していない時代に設計されているため、回路数や容量が不足していることが多くあります。
電子レンジ、IHクッキングヒーター、エアコン、ドラム式洗濯乾燥機など、高消費電力機器を同時に使うと、契約容量を超えてブレーカーが落ちる原因になります。
2. オフィス機器の増設
オフィスでは、パソコンや複合機、サーバー、ネットワーク機器など、多数の電源が必要です。
特にサーバーや業務用コピー機は常時稼働するため専用回路が推奨され、既存のブレーカーだけでは容量が足りなくなることがあります。
3. 200V機器の導入
エコキュートやEV充電器、業務用エアコンなど200V仕様の機器を導入する場合、専用のブレーカーと回路が必須です。
既存の分電盤に空きがない場合、ブレーカーの増設が必要となります。
ブレーカー増設工事の流れ
1. 電気使用量と容量の確認
まず、契約しているアンペア数(例:30A、40A、50A)と、現状の消費電力量を把握します。
電気工事士が計測器を使って使用状況を分析し、必要な容量と回路数を算出します。
2. 分電盤の状態確認
分電盤の空きスペース、配線状況、主幹ブレーカーの容量を確認します。
空きがない場合は、分電盤の交換も同時に行うことがあります。
3. 新規ブレーカーの設置
必要に応じて新しいブレーカーを分電盤に取り付け、専用回路を配線します。
200V機器の場合は、単相3線式での結線や電圧切り替えも行います。
4. 動作確認と安全試験
施工後は、絶縁抵抗測定や電圧測定を行い、過負荷や漏電の危険がないかをチェックします。
安全が確認できれば、施工完了です。
電気容量不足を解消する方法
ブレーカー増設だけでなく、以下の方法を組み合わせることで、より効率的に容量不足を解消できます。
【容量不足解消の具体策】
・ 契約アンペア数の引き上げ
電力会社に申請して契約容量を増やすことで、同時使用できる機器が増えます。
ただし、電気料金の基本料金も上がるため、必要に応じた設定が大切です。
・ 専用回路の設置
IHやエアコンなどの大電力機器には専用回路を設置し、他の回路への負荷を減らします。
・ 機器使用の分散
同時使用を避け、使用時間をずらすことで一時的に容量不足を防ぐことができます。
・ 省エネ家電への入れ替え
消費電力の少ない機器に更新することで、ブレーカーが落ちにくくなります。
ブレーカー増設工事の費用目安
ブレーカー増設工事の費用は、施工内容や分電盤の状態によって異なります。
一般的な目安は以下の通りです。
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| ブレーカー1基増設 | 約10,000~20,000円 |
| 専用回路追加(配線含む) | 約15,000~30,000円 |
| 分電盤交換 | 約40,000~80,000円 |
安全性確保のための注意点
・ 必ず有資格の電気工事士に依頼する
無資格施工は感電や火災のリスクが高く、法的にも禁止されています。
・ 将来の拡張性を考える
今後の家電や機器の増加を見越し、余裕のある容量設定にすることが重要です。
・ アフターサポートのある業者を選ぶ
施工後の不具合や増設にも迅速に対応してくれる業者が安心です。
ブレーカーの増設は、容量不足を根本から解決し、安全で快適な電気環境を実現するための重要な工事です。
次の見出しでは、オフィス環境における配線・照明・LAN工事の最適化プランについて、さらに具体的に解説します。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
オフィスの電気工事増設プラン!配線・照明・LAN工事の最適化術
オフィス環境の快適性や業務効率は、電気設備の計画性によって大きく左右されます。
特に、パソコンやネットワーク機器、複合機、照明設備など、多くの電力を消費する機器が集まるオフィスでは、電気工事の増設計画を立てることが非常に重要です。
ここでは、配線・照明・LAN工事を含めたオフィスの最適化プランを、長期的な視点とSEO的な視点の両面から詳しく解説します。
オフィスにおける電気工事増設の必要性
働き方の多様化による電源需要の変化
テレワークやフリーアドレス制の導入により、従来の固定席配置から可変的なレイアウトへの移行が進んでいます。
これにより、電源コンセントの位置や数の見直しが必要になるケースが増加しています。
IT機器の増加と安定稼働
サーバー、ネットワークスイッチ、無線アクセスポイントなど、常時稼働するIT機器が増えると、専用回路やブレーカーの増設が不可欠になります。
容量不足や電圧降下を防ぐための計画的な施工が重要です。
配線工事の最適化ポイント
1. コンセント配置の最適化
業務用デスクや会議室、受付周辺など、機器使用が集中する場所に十分な数のコンセントを配置します。
延長コードやタコ足配線を避けることで、火災リスクの低減と美観の維持が可能です。
2. 専用回路の導入
レーザープリンターやサーバー、業務用冷蔵庫など、高負荷機器には専用回路を用意します。
これにより、他回路への影響を最小限に抑え、安定した電力供給を実現します。
3. 配線ルートの美観配慮
露出配線はオフィスの印象を損なうため、可能な限り床下配線やモール施工で整理します。
床配線システムやOAフロアの導入も有効です。
照明工事の最適化ポイント
1. LED照明への全面切り替え
従来の蛍光灯からLED照明に切り替えることで、消費電力を削減できます。
さらに、寿命が長いため交換コストも削減可能です。
2. 照度と色温度の最適化
デスクワークエリアは昼白色(5000K前後)で集中力を高め、会議室や休憩室は電球色(3000K前後)でリラックス効果を狙うなど、用途に応じた照明設計を行います。
3. 人感センサーや調光機能の導入
使用頻度の低いエリアには人感センサーを設置し、不要な電力消費を防ぎます。
また、時間帯や自然光に応じて照度を自動調整する調光システムも有効です。
LAN工事の最適化ポイント
1. 有線LANの整備
無線LANだけに頼ると、接続が不安定になり業務効率が低下します。
サーバーや大量データ通信を行うPCには有線LANを優先し、通信速度と安定性を確保します。
2. 配線経路の計画
LANケーブルは、電源ケーブルと分離して配線することで、ノイズ干渉を防止します。
また、将来の機器増設を見越して予備ケーブルを敷設しておくと便利です。
3. 無線LANの補強
オフィス全体で安定したWi-Fi接続を確保するため、アクセスポイントを適切に配置します。
特に壁や間仕切りが多いオフィスでは、中継器やメッシュWi-Fiの導入も検討します。
オフィス電気工事増設の費用目安
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| コンセント増設(1口) | 約8,000~15,000円 |
| 専用回路追加 | 約15,000~30,000円 |
| LED照明への交換(1基) | 約10,000~30,000円 |
| LAN配線(1ポート) | 約10,000~20,000円 |
※配線距離や建物構造によって変動します。
オフィス電気工事の成功ポイント
・ 長期的なレイアウト変更を想定した配線計画を立てる
・ 安全性と省エネ性能を両立させる設備選び
・ 有資格の電気工事士に依頼し、施工品質を確保
・ アフターサポートの充実した業者を選定する
オフィスの電気工事増設は、単なる配線作業ではなく、企業の生産性や快適性を高めるための戦略的投資です。
次は、家庭やオフィスでよく行われがちな延長コードの使用リスクと、安全に増設工事を行うべき理由について詳しく解説します。
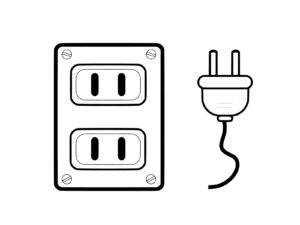
★ 電気工事の依頼方法についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
電気工事は便利屋でもOK?知っておきたい適切な依頼方法と選び方
延長コードは危険?安全な増設は電気工事士に依頼すべき理由
自宅やオフィスで電源不足を感じたとき、延長コードやタコ足配線で対応してしまうケースは少なくありません。
一時的な利用であれば便利に思えますが、長期間の常用は火災や機器トラブルの大きな原因になります。
ここでは、延長コードの危険性と、安全な増設工事を電気工事士に依頼すべき理由を詳しく解説します。
延長コードを常用する危険性
1. 発熱による火災リスク
延長コードは長時間・高負荷で使用すると、ケーブル内部で発熱し、被覆が劣化します。
特に電子レンジや電気ストーブ、ドライヤーなど消費電力の大きい家電を同時に使用すると、発火事故に直結する恐れがあります。
2. 接続部分の劣化と接触不良
差込口やプラグ部分は、長期間の使用や頻繁な抜き差しで金属接点が摩耗します。
これにより接触不良が発生し、異常発熱やスパーク(火花)が起こる危険があります。
3. 電圧降下による機器トラブル
延長コードを長く引き回すと、電圧降下が発生します。
パソコンやサーバーなど精密機器の場合、電圧が不安定になることでデータ消失や部品損傷を招く可能性があります。
安全な増設を行うための基本方針
延長コードはあくまで一時的な対策とし、恒久的な電源確保にはコンセント増設や専用回路の設置を行うことが安全です。
その際には、必ず有資格の電気工事士に依頼しましょう。
電気工事士に依頼すべき理由
1. 法令遵守と安全施工
電気工事は電気工事士法で規定されており、分電盤からの配線作業や壁内配線は第二種電気工事士以上の資格が必要です。
無資格で施工すると、感電や火災のリスクに加え、事故時に保険が適用されない可能性があります。
2. 正しい負荷計算と容量設計
電気工事士は使用機器の合計消費電力や既存回路の容量を計算し、過負荷を防ぐ増設プランを提案します。
これにより、ブレーカーが頻繁に落ちるといったトラブルを未然に防げます。
3. 美観とメンテナンス性の確保
配線ルートを考慮し、壁内配線やモール施工で見た目を損なわない工事が可能です。
また、将来の機器増設やレイアウト変更にも対応しやすいよう、予備回路や空きポートを確保する設計が行えます。
延長コード使用を避けるべきケース
以下の状況では、延長コードの常用は避け、早急に増設工事を検討すべきです。
・ 消費電力が1,000Wを超える機器を複数接続している
・ オフィスや店舗など、長時間連続使用が前提の環境
・ 電源コードが家具の下敷きになっている
・ ケーブルの発熱や変色が見られる
安全な電源確保のためのまとめ
・ 延長コードは短期間、軽負荷でのみ使用
・ 恒久的な電源確保はコンセント増設や専用回路設置で対応
・ 有資格の電気工事士による負荷計算、安全設計、美観配慮が不可欠
・ 法令遵守と長期的な安全性確保のため、自己施工は避ける
延長コードの便利さに頼りすぎると、知らぬ間に火災の危険性や機器寿命の短縮を招きます。
次の章では、特に注意が必要な古い住宅での増設電気工事のリスクと安全対策について詳しく解説します。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
古い住宅で増設電気工事を行う際のリスクと安全対策
古い住宅での電気工事増設は、新築や築浅物件とは異なり、配線や分電盤の老朽化、電気容量不足、施工基準の違いといった特有のリスクがあります。
特に築30年以上の住宅では、現代の家電使用状況を想定していない設計が多く、安全性の確保と計画的な施工が非常に重要です。
ここでは、古い住宅で増設工事を行う際に考慮すべきリスクと、安全に施工するための具体的な対策を解説します。
古い住宅における主なリスク
1. 配線の劣化と絶縁不良
築年数が経過した住宅では、ビニール被覆や布巻き配線が劣化している場合があります。
絶縁が弱くなると、漏電や感電、火災の原因となるため、増設工事前に必ず配線状態を確認し、必要に応じて全面的な配線交換を行うことが望まれます。
2. 分電盤の容量不足
昔の住宅では、契約容量が20A〜30A程度しかないことが多く、現代の高性能家電を複数使用すると頻繁にブレーカーが落ちる状態になります。
この場合、単純なコンセント増設だけでは解決せず、ブレーカー増設や契約アンペア数の引き上げが必要です。
3. アース未設置による感電リスク
古い住宅の多くは、アース(接地)工事が不十分です。
電子レンジや洗濯機など、アースが推奨される家電を未接続で使用すると、感電や機器故障の危険が高まります。
4. 施工基準の違い
建築当時の電気設備基準は、現在と比較して安全基準が緩く、コンセントの配置数や回路分けが不十分な場合があります。
現行基準に適合させるためには、大幅な配線計画の見直しが必要になることもあります。
安全対策と施工のポイント
1. 事前調査(現地診断)の徹底
工事前に有資格の電気工事士が現地調査を行い、配線の劣化状況、分電盤の状態、アースの有無を確認します。
調査結果に応じて、増設工事だけでなく補修や交換工事も同時に計画することが重要です。
2. 分電盤と配線の同時更新
老朽化が進んでいる場合は、増設と同時に分電盤や主幹ブレーカーの交換を行うことで、安全性と拡張性を確保できます。
また、太いケーブルへの交換により、将来の家電増設にも対応できます。
3. アース工事の追加
アースが未設置の場合は、増設工事に合わせて接地工事を行うことを推奨します。
特に水回りや屋外機器の設置時には必須です。
4. 専用回路の導入
IHクッキングヒーター、エアコン、EV充電器など、高負荷機器には必ず専用回路を用意し、他の回路への影響を防ぎます。
これにより、電圧降下やブレーカー落ちを防ぎ、機器寿命も延ばせます。
古い住宅での増設費用の目安
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| コンセント増設(1口) | 約10,000~15,000円 |
| 分電盤交換 | 約40,000~80,000円 |
| 配線交換(1回路) | 約15,000~25,000円 |
| アース工事 | 約8,000~15,000円 |
※配線距離や建物構造、劣化状況により変動します。
業者選びの注意点
・ 古い住宅の施工実績が豊富な業者を選ぶ
・ 事前調査を無料または低価格で行ってくれるか確認
・ 工事後の保証期間やアフターサポートの有無をチェック
・ 見積もり段階で追加費用の有無を明確にする
古い住宅での電気工事増設は、安全性と将来の利便性を両立するための重要なリフォーム要素です。
次の章では、多くの方が気になる電気工事の増設費用相場と、失敗しない業者選びのポイントについて詳しく解説します。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
電気工事の増設費用相場と賢い業者の選び方
電気工事の増設を検討する際、多くの方が気になるのは「費用はいくらかかるのか」という点です。
しかし、増設工事の費用は一律ではなく、工事内容・配線距離・建物構造・使用する部材の種類によって大きく変動します。
また、業者選びを誤ると、施工不良や過剰請求、保証の欠如といったトラブルに発展することもあります。
ここでは、電気工事の増設費用の相場と、失敗しないための賢い業者選びの方法を詳しく解説します。
電気工事の増設費用相場
コンセント増設
・ 一般的な室内での1口増設:8,000~15,000円
・ 壁内配線が困難な場合(露出配線、モール施工):10,000~18,000円
・ 専用回路付きコンセント(エアコン、IH対応):15,000~30,000円
ブレーカー増設
・ 1基追加:10,000~20,000円
・ 分電盤の容量変更、交換込み:40,000~80,000円
照明増設・LED化
・ シーリングライト設置:8,000~20,000円
・ LED照明器具への交換(1基):10,000~30,000円
LAN配線
・ 1ポート追加(有線LAN):10,000~20,000円
・ オフィス全体のLAN配線工事:50,000~200,000円
アース工事
・ 単独アース設置:8,000~15,000円
・ 水回り家電対応アース:10,000~18,000円
【ポイント】
費用の幅は、建物の構造(木造・鉄骨・RC)、配線距離、既存設備の状態によって変わります。
施工前に現地調査を受け、必ず複数の業者から見積もりを取ることが大切です。
賢い業者の選び方
1. 有資格者による施工か確認する
電気工事は第二種電気工事士以上の資格が必要です。
資格の有無はもちろん、経験年数や施工実績もチェックしましょう。
2. 見積もり内容の明確さ
見積もりは、工事内容・使用部材・配線距離・人件費・諸経費を明記している業者を選びます。
「一式〇円」とだけ記載されている見積もりは、後から追加請求が発生するリスクが高いです。
3. 現地調査の有無
現地調査をせずに見積もる業者は、施工後に追加工事や費用が発生する可能性があります。
必ず現地調査を行い、建物の構造や既存配線を確認したうえで見積もりを出してくれる業者を選びましょう。
4. アフターサポートと保証
施工後に不具合が出た場合、無料で再施工や修理に対応してくれる保証があるか確認します。
保証期間が1年以上ある業者は信頼性が高い傾向にあります。
5. 口コミ・評判の確認
インターネットの口コミサイトやGoogleレビュー、SNSで施工実績や利用者の声を確認しましょう。
特に「対応が丁寧」「説明が分かりやすい」といった評価は、施工品質の高さを示す指標となります。
業者選びで失敗しないためのチェックリスト
・ 有資格の電気工事士が在籍しているか
・ 現地調査を行ってくれるか
・ 見積書の明細が細かく記載されているか
・ 保証期間やアフターサービスが明確か
・ 過去の施工事例や口コミ評価が高いか
費用を抑えつつ高品質な工事を実現するコツ
・ 複数工事をまとめて依頼することで人件費を削減
・ 不要なオプションを外す
・ 繁忙期を避けて依頼すると割引が受けられる場合がある
電気工事の増設は、単なる配線作業ではなく、快適性・安全性・将来の拡張性を高めるための重要な投資です。
そして、正しい業者選びは、その投資を無駄にしないための最大のポイントです。
次の章では、今回解説してきたポイントを総括し、電気工事の増設を成功させるためのまとめをお届けします。

★ 電気工事業者についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
電気工事を成功させる第一歩!最適な業者を見つける検索の秘訣とは
まとめ
電気工事の増設は、快適な生活環境や業務環境を維持するために欠かせない工事です。
コンセントの増設、ブレーカーの増設、照明のLED化、LAN配線の最適化など、用途や目的に応じた施工を行うことで、日常の利便性は大きく向上します。
しかし、増設工事は単に「電源を増やす」だけでなく、安全性・将来性・コストパフォーマンスを総合的に考えた計画が必要です。
増設工事を行うべきタイミング
・ 新しい家電やOA機器を導入する前
・ ブレーカーが頻繁に落ちるようになったとき
・ オフィスや店舗のレイアウト変更時
・ テレワークやオンライン授業の開始時
・ 古い住宅で電気容量や配線の劣化が気になる場合
これらの状況に該当する場合は、早めに有資格の電気工事士へ相談することが重要です。
安全性確保が最優先
電気工事の増設は、無資格者が行うと感電・火災・漏電事故のリスクがあります。
特に分電盤からの回路増設や200V専用回路の敷設は、必ず第二種電気工事士以上の資格を持つ技術者に依頼してください。
施工後には絶縁抵抗測定や電圧確認を行い、安全性を保証してもらうことが大切です。
費用と業者選びのポイント
・ 複数の業者から見積もりを取り、費用相場を把握する
・ 見積書に工事内容と部材費の内訳が明記されているか確認
・ 現地調査を行い、追加費用が発生しないようにする
・ 施工後の保証期間やアフターサービスをチェック
・ 口コミや施工実績を確認して信頼性を確かめる
増設工事で得られるメリット
・ 快適性の向上
必要な場所にコンセントや照明を配置することで、生活や業務の効率が向上します。
・ 安全性の確保
延長コードやタコ足配線を減らし、火災や感電のリスクを低減できます。
・ 将来の拡張性
家電やIT機器の増加に対応できる配線計画をあらかじめ整備できます。
・ 省エネ効果
LED照明や適切な容量設計により、電気料金を削減できます。
まとめとしてのアドバイス
電気工事の増設は、「必要になったからやる」ではなく、「将来を見据えて計画する」ことが理想です。
特に新築やリフォーム、オフィス改装のタイミングは絶好のチャンスであり、配線計画を見直すことで長期的な安全性と快適性を確保できます。
そして、工事は必ず信頼できる有資格業者に依頼することが、費用面でも安全面でも最も賢い選択です。
そうすることで、電気容量不足や機器トラブルの心配がなくなり、日常生活や業務がストレスなく進められます。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
関連記事
 RANKING
RANKING
 CATEGORY
CATEGORY
- 2025年の崖
- DIY
- DX
- EV
- IoT
- IT
- ITインフラ
- LAN
- LANケーブル
- LAN配線
- LAN配線工事
- イーサネット
- イベント
- インターネット環境
- インターネット設備
- インターホン設備
- オフィス
- オンラインゲーム
- スマートホーム
- スマホ
- セキュリティ
- セキュリティ設備
- テレビ
- テレビ配線
- ドローン
- ネットワーク
- ネットワークサーバー
- ネットワーク設備
- ビジネスフォン
- フリーランス
- ブレーカー
- プレハブ
- ホームセキュリティ
- ホームページ
- マッチングアプリ
- マンション
- リサイクル
- リノベーション
- リフォーム
- 仕組み
- 仮設工事
- 依頼方法
- 個人事業主
- 倒産
- 儲かる
- 光回線
- 入退室管理
- 再生可能エネルギー
- 利益率
- 勘定科目
- 危険
- 名古屋
- 向いてない人
- 塾
- 壁
- 売上
- 大規模修繕
- 大阪
- 学童
- 宇宙エネルギー
- 将来性
- 屋内配線
- 工事
- 工場
- 幹線
- 建設業
- 弱電工事
- 接続
- 改修工事
- 放送設備
- 新しいビジネス
- 新築
- 最新技術
- 有線LAN
- 未来
- 検索
- 機械設備
- 水中ドローン
- 法人化
- 測量
- 漏電
- 火災報知器
- 無線LAN
- 無資格
- 現場代理人
- 現場監督
- 環境
- 産業利用
- 発電
- 相談
- 知識
- 福岡
- 空配管
- 経理
- 給電
- 耐用年数
- 自宅
- 見積書
- 見習い
- 計装工事
- 費用
- 軽微な工事
- 連絡アプリ
- 配線工事
- 配線方法
- 長崎
- 開業
- 防犯
- 防犯カメラ
- 離職
- 電気工事
- 電気工事会社
- 電気工事士
- 電気設備
- 電話設備







