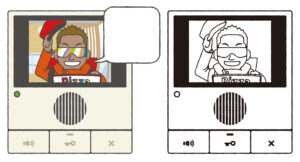インターホンの種類と特徴。モニター付き・ワイヤレス・スマート連携の違い
インターホンは、防犯・利便性・快適性を支える住宅設備として欠かせない存在です。
一見どれも同じように見えますが、実際には「モニター付き」「ワイヤレス」「スマート連携」といった複数のタイプが存在し、それぞれに配線方法・通信方式・電気工事の内容が異なります。
ここでは、主要な3タイプの特徴と違いを具体的に比較しながら解説します。
モニター付きインターホン。最も普及しているスタンダードタイプ
モニター付きインターホンは、現在最も一般的に普及しているタイプです。
玄関子機にカメラを内蔵し、屋内の親機に映像を映し出すことで「誰が来たかを確認してから応答できる」という安心感を提供します。
モニター付きタイプの特徴は以下のとおりです。
・ 有線接続(2芯またはLANケーブル)による安定通信
・ 録画機能付きモデルでは不在時の来訪者履歴も確認可能
・ 広角カメラ、夜間撮影対応で防犯性を強化
・ 電源はAC100VまたはPoE給電(LAN経由)
このタイプは電気工事士による配線工事が必要です。
玄関から親機までの距離や建物構造に合わせて、VVFケーブルまたはLANケーブルを壁内に通す施工が行われます。
特にマンションやオフィスでは、PoEスイッチを使って給電と通信を1本のLANケーブルで行うケースも増えています。
このタイプのメリットは、映像・音声ともに安定していることです。
ワイヤレスと比べて通信干渉が少なく、セキュリティ性・信頼性が高いのが特長です。
反面、設置位置を変える場合は再配線が必要なため、リフォーム時の計画性が重要になります。
ワイヤレスインターホン。工事不要で設置が簡単なタイプ
ワイヤレスインターホンは、無線通信を利用して親機と子機を接続するタイプです。
配線工事を行わずに設置できるため、賃貸住宅・仮設現場・倉庫・工事現場など、配線が難しい場所で多く利用されています。
ワイヤレス型の特徴をまとめると、次のようになります。
【ワイヤレスインターホンの基本特徴】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信方式 | 無線(2.4GHz帯・Bluetoothなど) |
| 電源 | 乾電池式・USB給電・ACアダプタ式 |
| メリット | 配線不要・設置が容易・移動も簡単 |
| デメリット | 電波干渉・距離制限・セキュリティリスク |
無線タイプの大きな魅力は、工事不要ですぐに設置できることです。
そのため、DIYでの導入やリフォーム前の一時的な運用にも適しています。
しかし、無線方式であるため、電子レンジやWi-Fiなどとの電波干渉が発生しやすい点に注意が必要です。
また、通信距離が長い場合(20〜30m以上)や鉄筋コンクリート構造の建物では、信号が届きにくくなることもあります。
さらに、セキュリティ上の脆弱性も課題の一つです。
最新モデルでは暗号化通信を採用していますが、業務用や防犯性を重視する現場では、有線接続のモニター付きタイプが推奨されます。
スマート連携インターホン。AI・IoT対応で進化する次世代型
スマート連携インターホンは、スマートフォン・AIスピーカー・クラウドシステムなどと連携する最新型のインターホンです。
近年では、AI顔認証・音声応答・遠隔操作などの高度な機能を備えたモデルが登場し、スマートホームの中心デバイスとして注目されています。
スマート連携型の代表的な特徴を見てみましょう。
・ スマートフォンアプリから遠隔応答や録画確認が可能
・ クラウド保存で過去の来訪履歴をいつでも確認
・ AI顔認証や音声認識で自動解錠や不審者検知
・ PoE、Wi-Fi、LAN接続など複数の通信方式に対応
例えば、外出中でもスマートフォンの通知から来訪者を確認し、アプリ上で「応答」や「解錠」操作を行うことができます。
また、防犯カメラやスマートロック、照明制御などと連携することで、一体型のホームセキュリティシステムを構築可能です。
このタイプを導入する際には、LAN配線やWi-Fi環境の整備が不可欠です。
PoE(Power over Ethernet)給電を利用する場合は、LANケーブルの規格(Cat6A以上)やスイッチングハブのPoE対応状況も確認する必要があります。
設置工事は電気工事士と通信工事士の両方のスキルが求められるケースが多く、プロによる施工が推奨されます。
さらに、クラウド連携型の機器は、定期的なファームウェア更新やネットワーク設定の見直しも必要です。
これにより、セキュリティ強化・通信安定化・新機能追加といったアップデートが継続的に行われ、長期的に安全に使用できます。
3タイプの比較まとめ
【インターホンの3タイプ比較】
| タイプ | 配線方式 | 特徴 | 適した環境 |
|---|---|---|---|
| モニター付き | 有線(2芯・LAN) | 安定・高画質・録画機能 | 一戸建て・マンション・オフィス |
| ワイヤレス | 無線通信(2.4GHz等) | 工事不要・簡単設置 | 賃貸・仮設現場・小規模住宅 |
| スマート連携 | LAN・Wi-Fi・PoE | AI・クラウド連携・遠隔応答 | スマートホーム・DXオフィス |
導入時の選定ポイント
インターホンを選ぶ際は、「建物構造」「通信環境」「利用目的」の3点を考慮することが重要です。
特に、以下の観点で検討すると失敗が少なくなります。
・ 鉄筋コンクリート造 → 有線型(通信安定)
・ 木造住宅や小規模オフィス → ワイヤレスでも可
・ スマート家電を導入予定 → スマート連携型
・ 高齢者や子どもがいる家庭 → モニター付きで録画機能あり
インターホンは単なる呼び出し装置ではなく、「暮らしの安心」と「住宅のDX化」を支える通信インフラです。
設置場所・配線ルート・電源方式を的確に設計し、専門の電気工事士による安全施工を行うことで、トラブルのない長期運用が実現します。
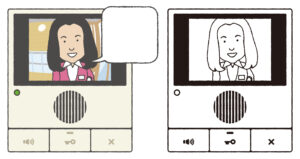
★ インターホンの配線工事について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
インターホンの配線工事とは?仕組み・配線方式・基本手順を完全解説