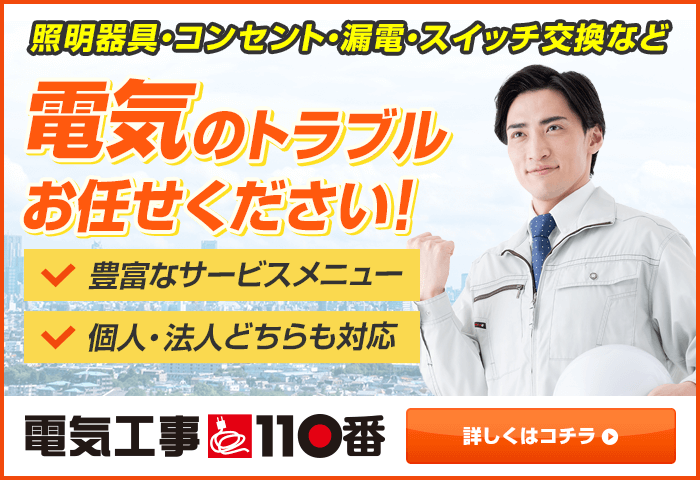テレビ配線工事は自分でできる?基本ポイント・DIYガイド
テレビ配線工事は、一見すると「ケーブルを差し込むだけ」と思われがちですが、実際には正しい配線ルートの設計・ケーブルの種類選び・接続部の確実な固定といった複数の要素が絡む作業です。
DIYで取り組むことは可能ですが、知識や準備不足のまま行うと画質低下や受信不良の原因になり、最悪の場合は再施工や追加費用が発生します。
そこで、ここでは初心者でも失敗しないための具体的な手順と注意点を詳しく解説します。
まずはDIY可能なテレビ配線工事の範囲を知る
テレビ配線工事には大きく分けて屋内配線工事と屋外配線工事があります。
【屋内配線工事】
テレビ本体とアンテナ端子を接続する、分配器を介して複数台のテレビをつなぐ、モールでケーブルを隠すなどの作業。
→ この範囲であればDIYでも対応可能です。
【屋外配線工事】
アンテナ本体の設置、屋根や外壁への配線固定、ブースター設置などの作業。
→ 高所作業や防水処理が必要なため業者依頼が推奨されます。
DIYを検討する場合は、自分ができる範囲と危険を伴う範囲を明確に線引きすることが大切です。
DIY前に必ず押さえる基本ポイント
1. ケーブルの種類選び
テレビ配線の肝は同軸ケーブルの性能です。
一般家庭でよく使われるのは4C-FBまたは5C-FBと呼ばれる規格で、数字が大きいほど太く、減衰が少なくなります。
・ 室内配線 → 4C-FBで十分
・ 長距離配線(10m以上)やBS/CS、4K・8K放送対応 → 5C-FBがおすすめ
さらに、シールド性能(2重、3重、4重)によってノイズ耐性が変わります。
4重シールドのケーブルは外来電波干渉を防ぎ、映像の乱れを最小限にできます。
2. 配線ルートの事前計画
DIYでは、作業前に配線ルートを紙に描き出すことを強くおすすめします。
ルート設計の際のチェックポイントは以下の通りです。
・ ケーブルが扉や引き出しの開閉に干渉しないか
・ 電源ケーブルと同じ束にせず、ノイズ源から離す
・ 露出配線の場合はモールやケーブルカバーで美観を保つ
・ 壁内配線では構造材や断熱材に干渉しないよう確認
この事前計画を怠ると、ケーブル長不足や再施工の手間が発生します。
3. 接続部分の処理と固定
接続部(テレビ端子や分配器、ブースターなど)でコネクタが緩んでいると信号が途切れやすくなります。
F型コネクタやネジ式のコネクタを使用し、確実に締め込み固定することが重要です。
また、屋外配線では接続部を自己融着テープで防水処理し、雨水や湿気の侵入を防ぎます。
DIY初心者がよくやる失敗とその回避方法
1. ケーブルの長さ不足
→ 必要長より1.2倍程度余裕を持って購入。
2. 曲げ半径が小さすぎる
→ 同軸ケーブルは急角度に曲げると内部の芯線が損傷し、減衰が増える。
3. 安価なケーブル・コネクタの使用
→ ノイズ耐性が低く、高画質放送でブロックノイズ発生の原因に。
4. 分配器の選定ミス
→ 接続するテレビ台数に応じた端子数・通過帯域を確認する。
失敗を防ぐ最大のコツは「材料選び」「事前計画」「確実な施工」です。
必要な工具と便利アイテム
DIYでテレビ配線工事を行う際にあると便利な工具とアイテムは以下の通りです。
・ ケーブルストリッパー(同軸ケーブルの皮むき用)
・ 圧着ペンチ(コネクタ固定用)
・ モール、ケーブルカバー
・ インシュロック(結束バンド)
・ 自己融着テープ(屋外用防水処理)
専用工具を使うことで作業時間短縮・仕上がり精度の向上が期待できます。
DIY成功の秘訣
テレビ配線工事は、基本的な知識と計画性があれば自分で行うことが可能です。
ただし、安易に始めるとケーブル劣化や画質低下といったトラブルを招きます。
・ ケーブルは規格とシールド性能を重視して選ぶ
・ 配線ルートを事前に設計し、余裕を持った長さを確保
・ 接続部は確実に固定し、屋外は防水処理を施す
この3つを徹底すれば、DIYでも業者施工に近い品質を実現できます。
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼


👉 急な電気工事も安心!信頼できる業者をすぐに手配するなら【電気工事110番】
電気工事はプロに任せるべき理由とは?
「突然、ブレーカーが落ちた」「コンセントが焦げている」「照明がチカチカする」──そんな電気のトラブル、意外と多くのご家庭やオフィスで起こっています。
しかし、これらのトラブルを自分で何とかしようとするのは非常に危険です。電気工事は国家資格が必要な作業であり、誤った対応は感電や火災の原因にもなりかねません。
また、以下のようなケースも電気工事の対象です。
・ コンセントやスイッチの増設や移設
・ 照明器具の交換やLED化工事
・ 漏電調査と対応
・ 分電盤やブレーカーの交換
・ エアコン専用回路の新設
こうした専門性の高い電気工事は、必ず資格を持つ業者に依頼することが鉄則です。
どこに頼めばいい?【電気工事110番】が選ばれる理由
「どこの業者に頼めばいいかわからない…」
そんな方にこそおすすめなのが、【電気工事110番】です。24時間365日受付、迅速対応が特長です。
電気工事110番の主な特長
| 特長 | 内容 |
|---|
| 全国対応 | 日本全国どこでも対応可能(※一部離島を除く) |
| 24時間365日受付 | 夜間・土日・祝日も電話一本で受付OK |
| 明朗会計 | 見積後の追加費用なし。納得の料金体系 |
| あらゆる電気工事にスピード対応 | 緊急時でもすぐに駆けつけてくれる迅速対応 |
| 豊富な施工実績 | 年間受付件数6万件以上の安心感 |
さらに、トラブル内容を相談すれば、その場で概算見積を提示してくれるため、費用面でも安心です。
よくある電気工事のトラブル例と対応事例
1. コンセントが焦げている・熱を持っている
→ 原因:配線の接触不良や電力オーバー
→ 対応:配線の交換、コンセントの安全基準対応への交換
2. エアコン設置の際に電源が足りない
→ 原因:専用回路が未設置
→ 対応:分電盤から専用回路を新設し、安全に使用可能に
3. 築年数の古い住宅での漏電調査
→ 原因:経年劣化やシロアリによる断線
→ 対応:回路全体のチェック+絶縁工事を実施し再発防止
このように、住まいの電気に関するお悩みは「電気工事110番」ひとつで解決可能です。
電気工事の相場ってどれくらい?安心の料金体系とは
「工事費が高額になるのでは…」と不安な方も多いかもしれませんが、電気工事110番では見積無料・明朗会計を徹底しています。
安心・安全な電気工事の第一歩は「相談」から!
今まさにトラブルが起きている方はもちろん、これからリフォームや増設を予定している方も、まずはプロに相談してみませんか?
電気工事で後悔しないために
電気工事は生活の安心・安全に直結する重要な作業です。
だからこそ、「安さ」だけで業者を選ぶのではなく、「実績」「対応力」「信頼性」で選ぶことが非常に大切です。
そのすべてを備えた【電気工事110番】なら、
✅緊急時も対応
✅見積無料
✅安心価格
で、あなたの住まいの電気トラブルをしっかり解決してくれます。
電気に関するお困りごとは、迷わず【電気工事110番】へご相談ください。
👇 下のリンクから『無料相談・見積依頼』が可能です / 今すぐチェックを!!
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼
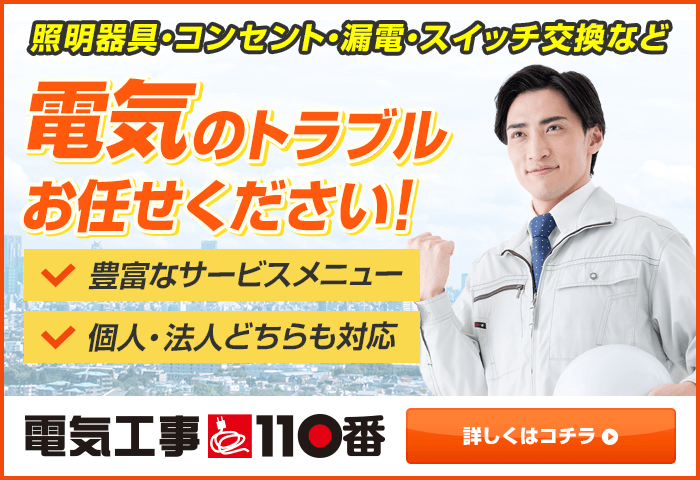
テレビ配線工事を自分で行う前に知っておきたい安全対策と注意事項
テレビ配線工事は、電気工事士が行う高電圧の電気配線と比べると低電圧機器の取り扱いが中心のため、感電リスクは低いとされています。
しかし、「低リスク=安全」ではありません。
DIYでの作業は、施工環境や作業方法によっては転落・切創・機器損傷・長期的な故障リスクを伴います。
そこで、作業前に必ず押さえておくべき安全対策と注意事項を、屋内作業と屋外作業に分けて詳しく解説します。
屋内配線工事の安全対策
1. 作業場所の確保と整理
配線工事では工具・ケーブル・部品を床に広げるため、作業スペースが狭いと転倒や部品紛失の原因になります。
作業前に家具や物を移動させ、1.5〜2m程度の作業空間を確保しましょう。
2. 電源を必ず切る
ブースターや分配器には電源が接続されている場合があります。
作業前には必ずコンセントからプラグを抜くか、スイッチを切って通電を遮断します。
通電状態でのケーブル着脱は機器内部の回路を損傷させる恐れがあります。
3. 工具の安全使用
ケーブルストリッパーや圧着ペンチなどの工具は、正しい方向・力加減で使用することが重要です。
誤った使い方はケーブルの芯線を傷つけ、接触不良や信号劣化を招きます。
屋外配線工事の安全対策
1. 高所作業時の注意
屋外のアンテナや外壁に配線を通す場合、脚立やはしごを使用します。
必ず水平で安定した場所に設置し、足元を確認してから昇降します。
可能であれば2人1組で作業し、一方がはしごを支えると安全性が向上します。
2. 天候条件の確認
雨や雪、強風時の屋外作業は感電・滑落・工具落下のリスクがあります。
特に冬季は霜や氷結によって足元が滑りやすくなるため、晴天かつ無風の日に作業することを徹底しましょう。
3. 防水・防錆処理
屋外配線では、接続部を自己融着テープや防水キャップで覆い、雨水や湿気の侵入を防ぎます。
これを怠ると、腐食や接触不良による受信障害が数か月〜数年後に発生します。
共通の注意事項
・ 無理な姿勢での作業は避ける
腕や腰に負担がかかり、長時間作業による疲労が事故の原因となります。
・ 壁や床の内部構造を確認する
下地材や配管・電線を傷つけると、修復費用が高額になります。
壁裏探知機や施工図面を活用しましょう。
・ 部材は必ず規格品を使用
安価な非規格部材は性能不足や安全性の欠如につながります。
【安全対策チェックリスト】
| チェック項目 | 屋内 | 屋外 |
|---|
| 作業スペースの確保 | ○ | ○ |
| 電源オフ | ○ | ○ |
| 工具の安全使用 | ○ | ○ |
| 脚立・はしごの安定 | – | ○ |
| 天候確認 | – | ○ |
| 防水・防錆処理 | – | ○ |
DIYでテレビ配線工事を行う際は、「時間をかけても安全優先」が鉄則です。
少しの油断が大きな事故につながるため、上記のポイントを確実に守ることが、快適で長持ちするテレビ環境を実現する第一歩になります。

★ テレビに関する内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!
テレビにLANケーブルをつなぐ理由:今すぐ実践すべき理由
▼ 電気工事に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番>▼